| 海 蔵 寺 かいぞうじ |
 |
| DATA |
| 山号寺号 |
扇谷山海蔵寺 |
| 宗 派 |
臨済宗 |
| 住 所 |
扇ガ谷4-18-8 |
| 拝観時間 |
9:30~16:00 |
| 拝 観 料 |
100円 |
| 交 通 |
鎌倉駅西口 徒歩20分 |
| H P |
|
|
| 概 要 |
・1253年、鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王の命により真言宗の寺を建立するも幕府滅亡時に消失、1394年に鎌倉公方の足利氏満の命により心昭空外を開山として再興した。心昭空外は「殺生石伝説」で知られる源翁禅師のこと。
・本尊の薬師如来像は別名「啼薬師(なきやくし)」とも「児護薬師(こもりやくし)」とも呼ばれている。寺の裏から聞こえる赤ん坊の泣き声を玄翁禅師がたどっていくと、甘い香りが漂い光り輝く墓があり、掘ってみると薬師様の顔が現れたため、新たに彫った薬師如来像の胎内にそれを納めたという。胎内の像は61年に一度公開される。
・門前に鎌倉十井のひとつ、「底脱の井」がある。また境内の左奥のやぐら内には16の穴が掘られた「十六の井」がある。
・「東国花の寺百ヶ寺」のひとつに数えられる花の寺として知られている。
・鎌倉三十三所観音霊場の第26番札所。 |
|
|
|
|
| 岩船地蔵堂 |
 |
亀ヶ谷坂を下ったところに源頼朝の娘・大姫の守本尊を祀っている六角形の御堂がある。この御堂は「岩船地蔵堂」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵のひとつ(第十五番)となっている。
堂内奥に本佛となる石造地蔵尊、その前に木造地蔵尊を安置し供養おり、現在では木造の地蔵尊しか拝観することができない。石像の守り本尊の後光が船首を上にした船の形に造られている舟形光背(ふながたこうはい)となっており、石(岩)の舟(船)から「岩船地蔵」という名前になったという説がある。
許婚との仲を裂かれた大姫が傷心のまま亡くなり、これを哀れんだ御家人たちがこの地に野辺送りをしたといわれている。
なお、「岩船地蔵尊」の御朱印は海蔵寺で授与される。
|
|
| 境内の風景 |
 |
 |
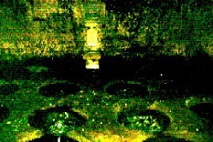 |
| 穏やかな雰囲気の境内です。 |
山門前に「底脱の井」があります。 |
境内奥のやぐら内に「十六の井」があります。 |
|
| 舞台となった作品 |
|
|
  |