| . |
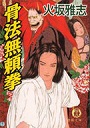 |
|
あらすじ
バサラ者から凌辱された娘を助け出した堀辺牙王丸は、その腕を買われ堀越公方・足利政知のもとへ連れていかれた。政知は政情不安な鎌倉入りを果たすため、彼に手助けしてほしいというのだ。牙王丸は政知の力になることを了承すると、まずは行方知れずとなっている政知の側近・京極定次を探すことになった…。
|
|
| 作品の舞台 |
高徳院・・・大仏の中では、夜ごと賭博が行われています。
本覚寺・・・牙王丸と小夜が再会します。
鶴岡八幡宮・・・バサラ者集団の「黒竜党」の根城になっています。
称名寺・・・牙王丸たちは、頼朝の秘宝を探すために金沢文庫に向かいます。 |
|
| 登場人物 |
| 堀辺牙王丸 |
常陸佐竹氏の分家・堀辺家の次男。放蕩無頼な骨法の達人。 |
| 足利 政知 |
堀越公方。鎌倉入りを望んでいる。8代将軍・足利義政の弟。 |
| 京極小次郎定次 |
政知の側近。22歳。行方知れずとなっている。 |
| 鬼阿弥 |
政知の配下。能楽師。 |
| 小夜 |
牙王丸の友人。父の菩提を弔うため霊場まわりをしている。 |
| 浄覚房慈空 |
称名寺の僧。小夜の伯父。 |
| 銀夜叉 |
バサラ者集団「大神一門」の頭領。 |
| 獣人 |
「大神一門」の仲間。小さい頃から狼に育てられる。 |
| 香蘭 |
バサラ者集団「黒竜党」の女頭領。 |
| 法華ノ与藤次 |
「黒竜党」の組頭。 |
| 仏ノ文佐 |
「黒竜党」の組頭。 |
| 極楽寺衆 |
鎌倉の治安を悪化させているバサラ者。 |
| 座元 |
大仏像の中で賭場を開く座元。 |
| 若者 |
座元の配下。 |
| 娘 |
賭場で凌辱される京の公家の娘。 |
| 長老 |
丹沢山麓にある村の長老。 |
| 朱音 |
丹沢山麓にある村の娘。 |
| 男 |
丹沢山麓にある村の男。朱音とは良い仲。 |
| 観世 信光 |
鬼阿弥の能の師。世阿弥の血をひく。 |
|
| . |
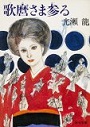 |
|
あらすじ
御前試合で剣客・鈴木清兵衛邦教に敗れた三浦縦横斎重国は、その後悶々とした生活を送っていた。しかし、清兵衛の息女・多紀の姿を町中で一目見てから、彼は自らを戒め再び剣の道を究めようとするのだが…。
|
|
| 作品の舞台 |
御霊神社・・・縦横斎は清兵衛との再試合の策を練るために、一人で御霊神社に参詣します。
長谷寺・・・如安が籍を置くのは、長谷寺の末院・常智院です。 |
|
| 登場人物 |
| 三浦縦横斎重国 |
根津に天地神明流の道場をもつ剣客。27~8歳。 |
| 鈴木清兵衛邦教 |
本所に神武尺獲流の道場をもつ剣客。 |
| 多紀 |
清兵衛の息女。 |
| 横山四方次郎 |
縦横斎の高弟。 |
| 三枝鎮四郎 |
清兵衛の高弟。 |
| 菊池伝七郎 |
清兵衛の高弟。佐賀藩士。 |
| 松平越中守定信 |
清兵衛の弟子。新甲乙流を開く。後の老中。 |
| 徳川 家光 |
江戸幕府3代将軍。 |
| 柳生但馬守宗矩 |
惣目付。家光の武芸の指南役。 |
| 後藤田信濃守秋広 |
幕府の重臣。 |
| 正田越中守長成 |
幕府の重臣。 |
| 石田孫四郎 |
芝巴町で道場をもつ縦横斎の剣の師。 |
| 滝野 遊軒 |
清兵衛の剣の師。起倒流の達人。 |
| 松山主水大吉 |
名護屋の剣客。二階堂平法の達人。 |
| 松林左馬助永吉 |
名古屋の剣客。願立流の達人。 |
| 如安 |
長谷寺末院・常智院の僧。 |
| 鎌倉権五郎景政 |
御霊神社の祭神の霊。 |
|
| . |
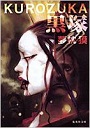 |
|
あらすじ
鎌倉から追われる身となった九郎坊と大和坊は深い森をさまよう中、一軒の家に一夜の宿を請うことになった。その家には一人で住む「黒蜜」と名乗る女は、自分の寝床となる奥の間を覗かないことを条件に逗留を許すのだが…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・大和坊は九郎坊を裏切り、鎌倉方に寝返ります。
|
|
| 登場人物 |
| 九郎坊 |
熊野から諸国行脚をしている僧。「源義経」。 |
| 大和坊 |
熊野から諸国行脚をしている僧。「弁慶」。 |
| 黒蜜 |
千年以上吸血鬼として生き続ける不死身の女。現世では「蜜夜」「魂蜜」と名乗る。 |
| クロウ |
九郎坊の現世での名前。 |
| 赤帝 |
大和坊の現世での名前。関西の実力者。赤帝軍の長。 |
| ライ |
赤帝に従う30代前半の女。 |
| 沙仁輪 |
武器売買組織「埴輪」を率いる埴輪王の一人。 |
| 居座魚 |
埴輪王の一人。 |
| トンバ |
埴輪王の一人。 |
| 歌留多 |
埴輪の一員。 |
| 九遠 |
埴輪の一員。 |
| イサム |
埴輪の一員。 |
| タツヤ |
埴輪の一員。 |
| 白王 |
関東の実力者。白王軍の長。 |
| 長谷川 |
白王の部下。 |
| 横山 広明 |
白王の部下。行方不明。 |
| 源 頼朝 |
九郎坊の兄。 |
| 藤原 泰衡 |
九郎坊を追う東北の雄。 |
| 水元 六蔵 |
ヤマト財閥の実力者。後の「赤帝」。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
剣道部に所属する高校生の白石友恵、原口武蔵、北村志郎は学校からの帰り道に、雷鳴が轟くと共に姿を消した。そして3人が目を覚ますと、そこは平安末期の世。彼らは歴史の波に呑み込まれていくのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
大倉幕府・・・頼朝の呼び出しを受けた四郎義時は、大倉幕府(頼朝屋敷)で文覚上人を見かけます。
|
|
| 登場人物 |
| 白石 友恵 |
高校生。女子剣道部の主将格。 |
| 原口 武蔵 |
高校生。男子剣道部の主将格。友恵とはいい仲。 |
| 北村 由紀 |
高校生。女子剣道部の副将格。友恵の親友。 |
| 北村 志郎 |
由紀の弟。 |
| 白石 雄介 |
友恵の兄。 |
| 源次郎義仲 |
源義賢の次男。幼名・駒王丸。友恵の夫となる。 |
| 中原 兼遠 |
木曾の豪族。 |
| 樋口次郎兼光 |
兼遠の長男。義仲の四天王の一人。 |
| 今井四郎兼平 |
兼遠の次男。義仲の四天王の一人。 |
| 根井 行親 |
重臣。義仲の四天王の一人。 |
| 楯 親忠 |
重臣。義仲の四天王の一人。 |
| 木曾 義高 |
義仲と友恵の息子。 |
| 海野小太郎 |
義高の従者。 |
| 桔梗 |
中原屋敷の侍女。駒王丸の育ての母。 |
| 太夫坊覚明 |
駒王丸に手習いを教える僧。 |
| 源九郎義経 |
源義朝の九男。幼名・牛若丸。平家追討に大活躍する。 |
| 伊勢三郎義盛 |
義経の家来。 |
| 佐藤 嗣信 |
義経の家来。 |
| 佐藤 忠信 |
義経の家来。嗣信の弟。 |
| 源 義朝 |
源氏の棟梁。 |
| 源 義賢 |
義朝の弟。義仲の父。 |
| 源 行家 |
義朝の末弟。 |
| 源 義平 |
義朝の長男。「鎌倉悪源太義平」と呼ばれる。 |
| 源 頼朝 |
義朝の三男。鎌倉幕府初代征夷大将軍。 |
| 北条 政子 |
頼朝の妻。のちに「尼将軍」と呼ばれる。 |
| 大姫 |
頼朝の長女。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。頼朝の懐刀。 |
| 北条三郎宗時 |
時政の三男。伊東祐親軍に討たれる。 |
| 北条四郎義時 |
時政の四男。のちに二代執権となる。 |
| 仁田 忠常 |
御家人。時政の腹心。 |
| 梶原 景時 |
御家人。頼朝の軍師的存在。 |
| 梶原 景季 |
御家人。景時の長男。 |
| 畠山 重能 |
御家人。 |
| 佐々木高綱 |
御家人。 |
| 和田 義盛 |
御家人。侍所初代別当。 |
| 平 清盛 |
平家の棟梁。 |
| 平 重盛 |
清盛の長男。 |
| 平 宗盛 |
清盛の三男。 |
| 平 知盛 |
清盛の四男。 |
| 平 維盛 |
重盛の嫡男。 |
| 中宮 徳子 |
清盛の次女。「建礼門院徳子」と呼ばれる。 |
| 安徳帝 |
81代天皇。母は建礼門院。 |
| 後白河法皇 |
77代天皇。院政を敷く朝廷の実力者。 |
| 冷泉の局 |
法皇の愛寵。 |
| 二位の局 |
清盛の正妻。 |
| 俊寛 |
法皇の側近。 |
| 青柳 |
中宮付きの侍女。 |
| 以仁王 |
法皇の第二皇子。 |
| 北陸宮 |
以仁王の遺児。 |
| 遠藤 盛遠 |
野伏。呼称は「阿修羅」。後に真言宗の僧「文覚」となる。 |
| 渡辺渡左衛門尉 |
盛遠の従兄弟。豪族。 |
| 袈裟 |
渡の嫁候補。15歳。盛遠が横恋慕する。 |
| 衣川 |
袈裟の母。 |
| 山木 兼隆 |
伊豆国の代官。 |
| 石田次郎為久 |
相模国の武士。 |
| 藤原 秀衡 |
藤原氏の棟梁。 |
| 藤原 国衡 |
秀衡の長男。 |
| 藤原 泰衡 |
秀衡の次男。 |
| 金売り吉次 |
商人。義経の手助けをする。 |
| 氷室 |
藤原家の賄い女。不思議な能力を持つ。 |
| 了然 |
和尚。身寄りのない子供たちの世話をする。 |
| リキ |
身寄りのない子供。リーダー格。 |
| 由衣 |
身寄りのない子供。 |
| 沙夜 |
身寄りのない子供。 |
| 黒兵衛 |
身寄りのない子供。 |
| 伍助 |
身寄りのない子供。 |
| ロク |
身寄りのない子供。 |
| カラス |
身寄りのない子供。 |
| 鈴 |
身寄りのない子供。唖の少女。 |
| 静 |
身寄りのない子供。後に磯良に拾われ、白拍子となる。 |
| 磯良 |
白拍子。 |
| 胡蝶 |
白拍子。 |
|
| . |
 |
| 鎌倉しらす茶屋 |
武者王寺流 |
ブイツー
ソリューション |
|
あらすじ
無双直伝英信流居合いを遣う浪人・早船飛十郎。彼は一人の町娘を助けたことから、娘の祖父・安達屋藤兵衛と知り合い、藤兵衛が元締めをつとめる「仇討ち屋」の配下となった。「仇討ち屋」とは、本人に代わって仇を探し出し仇討ちの手助けをする稼業で、決して本人に代わっての仇討ちはしないというものだった。その最初の仕事が、鎌倉で行われるのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
化粧坂・・・早苗たちは、化粧坂で父の敵討ちをします。
|
|
| 登場人物 |
| 早船飛十郎 |
仇討ちの助太刀人「仇討ち屋」の一員。無双直伝英信流居合の達人。 |
| 安達屋藤兵衛 |
「仇討ち屋」の元締。表の顔は両国の芝居小屋や見世物小屋の元締。 |
| 木村 新吾 |
「仇討ち屋」の一員。若い浪人者。 |
| 伊蔵 |
「仇討ち屋」の目役(監視役)。 |
| 奈津 |
藤兵衛の孫娘。 |
| 小吉 |
藤兵衛贔屓の深川芸者。町火消しの小頭の妹。 |
| 米倉 早苗 |
東海筋のさる藩の馬廻り役の娘。19歳。今回の仕事の「討ち人」。 |
| 米倉英之進 |
早苗の弟。13歳。今回の仕事の「討ち人」。 |
| 小野田平右衛門 |
早苗の父の同僚の早苗と英之進の仇。今回の仕事の「討たれ人」。 |
| 大蛇の辰造 |
両国の地回りの兄貴分。小悪党。 |
| 林崎甚助重信 |
無双直伝英信流の流祖。 |
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
父の仇として頼家の遺児・公暁は、叔父の実朝を暗殺した。そしてその首を三浦の郎党・弥源太にあずけたのだが、その後弥源太は首とともに失踪してしまう。いったい、彼と実朝の首はどこへ行ってしまったのか・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・公暁が源実朝を暗殺します。
若宮大路・・・弥源太と常晴は、頼茂の宿坊を出たあと若宮大路を歩きます。
稲村ガ崎・・・鞠子の屋敷があります。
高円坊・・・朝盛は、寺を構え高円坊と名乗ります。
 |
和田家の所領だった三浦市初声には「高円坊」というバス停もあります。 |
|
|
| 登場人物 |
| 源 実朝 |
鎌倉幕府3代将軍。 |
| 源 頼家 |
鎌倉幕府2代将軍。実朝の兄。修善寺へ幽閉、暗殺される。 |
| 北条 政子 |
頼家、実朝の母。尼将軍。 |
| 公 暁 |
頼家の次男。鎌倉別当阿闍梨。 |
| 栄 実 |
頼家の三男。5年前に自害。 |
| 禅 暁 |
頼家の四男。 |
| 鞠 子 |
頼家の娘。後に「竹御所」と呼ばれる。 |
| 加 賀 |
鞠子の侍女。 |
| 小 藤 |
鞠子の侍女。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。 |
| 牧 の 方 |
時政の後妻。 |
| 北条 義時 |
鎌倉幕府2代執権。時政の子。政子の弟。 |
| 姫 の 前 |
義時の前妻。元・頼朝の侍女。 |
| 比企 朝宗 |
姫の前の父。 |
| 伊 賀 局 |
義時の後妻。 |
| 北条 政村 |
伊賀局の連れ子。 |
| 北条 光宗 |
政所執事。伊賀局の兄。 |
| 北条 時房 |
時政の子。義時の弟。初代六波羅探題。 |
| 大江 広元 |
幕府の有力御家人。出家後、法名は「覚阿」。 |
| 大江 時広 |
広元の子。 |
| 平賀 朝雅 |
牧の方の娘婿。京都守護。 |
| 伊賀 光季 |
京都守護。 |
| 伊賀 光綱 |
光季の次男。 |
| 三浦 義村 |
幕府の有力御家人。 |
| 三浦 義澄 |
義村の父。 |
| 駒 王 丸 |
義村の子。後の「三浦 光村」。 |
| 三浦 胤義 |
義村の弟。 |
| 武 常晴 |
三浦の郎党。 |
| 弥 源 太 |
三浦の郎党。公暁の乳母子。 |
| 和田 義盛 |
幕府の有力御家人。侍所初代別当。 |
| 杉本 義宗 |
義盛の父。 |
| 朝夷名三郎義秀 |
義盛の三男。 |
| 和田(金窪)義直 |
義盛の四男。 |
| 和田 義重 |
義盛の五男。 |
| 和田 胤長 |
義盛の甥。 |
| 和田 朝盛 |
義盛の孫。 |
| 笙 子 |
和田家の姫。弥源太の許嫁。 |
| 安達 盛長 |
幕府の有力御家人。 |
| 安達新三郎 |
盛長の孫。御使雑色。 |
| 長尾新六定景 |
幕府の御家人。 |
| 長尾太郎景茂 |
定景の長男。 |
| 長尾次郎胤景 |
定景の次男。 |
| 波多野義常 |
幕府の御家人。自害。 |
| 波多野忠綱 |
義常の弟。 |
| 武田 信光 |
幕府の御家人。 |
| 結城 朝光 |
幕府の御家人。 |
| 山内左衛門尉 |
幕府の御家人。 |
| 筑後四郎兵衛尉 |
幕府の御家人。 |
| 金窪兵衛尉行親 |
幕府の御家人。 |
| 加藤 次郎 |
幕府の御家人。 |
| 二階堂行光 |
幕府の御家人。 |
| 阿野 時元 |
駿河の御家人。 |
| 千葉 成胤 |
上総の豪族。 |
| 泉 親衡 |
信濃の豪族。 |
| 青栗 七郎 |
泉の郎党。 |
| 安 念 坊 |
七郎の弟。 |
| 源 仲章 |
実朝の側近。 |
| 後白河法皇 |
第77代天皇。院政を敷く朝廷の実力者。 |
| 高倉 上皇 |
第80代天皇。 |
| 守貞 親王 |
高倉上皇の二宮。後の後高倉上皇。 |
| 惟明 親王 |
高倉上皇の三宮。 |
| 尊成 親王 |
高倉上皇の四宮。 |
| 後鳥羽上皇 |
第82代天皇。後白河法皇につづき院政を敷く。 |
| 伊 賀 局 |
後鳥羽上皇の寵妃。元・白拍子「亀菊」。 |
| 西 御 方 |
後鳥羽上皇の寵妃。 |
| 冷泉宮頼仁親王 |
後鳥羽の四宮。西御方の子。 |
| 本 覚 尼 |
西御方の妹。実朝の正室。 |
| 春華門院 |
後鳥羽上皇の娘。 |
| 土御門天皇 |
第83代天皇。 |
| 承明門院 |
土御門天皇の生母。 |
| 藤原 兼子 |
卿局。 |
| 藤原 秀康 |
後鳥羽上皇の側近。 |
| 坊門 忠信 |
公家。権大納言。西御方の兄。 |
| 西園寺実氏 |
公家。権中納言。 |
| 藤原 国通 |
公家。参議。 |
| 平 光盛 |
公家。散位。 |
| 難波 宗長 |
公家。刑部卿。 |
| 源 頼茂 |
公家。右馬権頭。 |
| 源 頼兼 |
公家。頼茂の父。 |
| 源 通親 |
公家。朝廷の実力者。 |
| 藤原 忠綱 |
公家。朝廷の仕官。 |
| 一条 能保 |
公家。頼朝の妹の婿。死亡。 |
| 一条 実雅 |
公家。能保の子。 |
| 九条 道家 |
公家。左大臣。 |
| 三 寅 |
道家の子。後の「藤原 頼経」。 |
| 交野 八郎 |
後鳥羽上皇に仕える元・京の盗賊。 |
| 茜 丸 |
八郎の従者。 |
| う つ ぼ |
八郎の従者。 |
| 四 天 |
八郎の従者。 |
| 陳 和 卿 |
宋人の工匠。 |
|
| . |
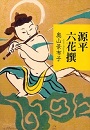 |
|
あらすじ
吉野の山で九郎と別れた静は、北条方に捕えられ鎌倉に連れてこられた。安達新三郎の邸に預けられた彼女は、九郎のことについて北条方に詰問されるのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・静は、北条方の前で舞を舞います。
安達新三郎邸・・・鎌倉へ連れてこられた静は、安達新三郎邸に預けられます。 |
|
| 登場人物 |
| 静 |
白拍子。北条方に捕えられ鎌倉に連れてこられる。 |
| 源九郎義経 |
平家追討の源氏方の大将。静を愛妾としている。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。 |
| 北条 政子 |
頼朝の妻。 |
| 梶原 景時 |
幕府の重臣。頼朝の腹心。 |
| 工藤 祐経 |
幕府の御家人。 |
| 安達新三郎 |
幕府の御家人。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鶴岡八幡宮で公暁の門弟として過ごしてきた駒若丸は、騒ぎを起こし八幡宮への出仕を停められた時期に元服し、名を「三浦光村」と変えて武士となった。そして公暁も将軍で叔父の源実朝を暗殺し、幕府は新たに京から将軍を連れてくることになった。そんな折光村は父・義村から次期将軍の近習となることを伝えられた。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・駒若丸は公暁の門弟として八幡宮に出仕していました。
西御門・・・三浦泰村邸があります。
永福寺・・・宝治合戦で光村が戦います。
法華堂・・・追い詰められた三浦一族は、頼朝の墓がある法華堂に集結します。 |
|
| 登場人物 |
| 三浦 義村 |
幕府の有力御家人。策略家。 |
| 三浦 泰村 |
義村の次男。父の死後、三浦家当主となる。 |
| 三浦三郎光村 |
義村の四男。八幡宮へ出仕していたが、元服して武士となる。幼名「駒若丸」。 |
| 三浦 家村 |
義村の六男。 |
| 千草姫 |
光村の正室。 |
| なづな |
光村の側室。 |
| 三浦 範村 |
光村と千草の長男。幼名「駒王丸」。 |
| 花梨 |
光村と千草の長女。 |
| 光音丸 |
光村となづなの長男。 |
| 葉山 |
千草の乳母。 |
| 仙太 |
光村の下男。 |
| 卍 |
千草の下男。 |
| 源 頼家 |
鎌倉幕府2代将軍。死亡。 |
| 源 実朝 |
頼家の弟。鎌倉幕府3代将軍。 |
| 公暁 |
頼家の子。鶴岡八幡宮寺別当。 |
| 坊門姫 |
頼朝の同母妹。頼経の曾祖母。 |
| 鞠子姫 |
頼家の娘。公暁の異母妹。竹御所。頼経の妻。 |
| 北条 政子 |
頼朝の正室。尼御台。 |
| 北条 義時 |
政子の弟。鎌倉幕府2代執権。 |
| 北条 泰時 |
義時の長男。鎌倉幕府3代執権。 |
| 北条 経時 |
泰時の嫡孫。鎌倉幕府4代執権。 |
| 北条 時頼 |
経時の長弟。鎌倉幕府5代執権。 |
| 北条 時定 |
経時の次弟。 |
| 名越 朝時 |
義時の次男。名越流当主。 |
| 名越 光時 |
朝時の長男。 |
| 名越 時長 |
朝時の三男。 |
| 名越 時幸 |
朝時の四男。 |
| 藤原 頼経 |
鎌倉幕府4代将軍。九条家と西園寺家の血筋。幼名は「三寅」。 |
| 九条 道家 |
頼経の父。 |
| 西園寺倫子 |
頼経の母。 |
| 結城 朝広 |
頼経の近習。 |
| 大江 広元 |
政所別当。幕府の重鎮。 |
| 毛利 季光 |
広元の四男。妻は三浦家の姫。 |
| 和田 義盛 |
侍所別当。和田合戦で戦死。 |
| 安達 景盛 |
元・反三浦派の有力御家人。実朝の死後「高野入道」として出家。 |
| 安達 義景 |
景盛の嫡男。幕府の御家人。 |
| 備中阿闍梨 |
雪ノ下北谷に住む公暁の後見者。 |
| 後鳥羽上皇 |
第82代天皇。院政を敷く朝廷の実力者。 |
| 順徳上皇 |
第84代天皇。 |
| 後堀河天皇 |
第86代天皇。 |
| 西園寺公経 |
朝廷の内大臣。 |
|
| . |
 |
| 帰来草 かねさわかまくら時超え奇譚 |
松崎雅美 |
正光堂 |
|
あらすじ
剣道が好きな高校生・篠原摩利伽は花火大会を見に行く途中、首都圏直下型地震の被害にあい気を失ってしまい、気がつくとそこは鎌倉時代の金沢郷だった。地元の村人たちは突然現れた見知らぬ彼女を「赤髪の天狗」と恐れていたが、そんな摩利伽に手を差し伸べたのが当時の幕府の重臣・北条実時だった。実時はとっさの機転で、摩利伽を「摩利支天」としてあがめることで村人たちを治めたのだが…。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・摩利伽は、「摩利支天」として幕府の安定と繁栄を祈願する神事を行います。
若宮大路・・・摩利伽と太郎は、道沿いに地震で被災し困窮する民の姿を目にします。 |
|
| 登場人物 |
| 篠原摩利伽 |
剣道道場に通う女子高生。17歳。物おじせず明るい性格。 |
| 北条 実時 |
金沢郷に邸を持つ幕府の評定衆。 |
| 北条 長時 |
鎌倉幕府6代執権。実時の従弟。京都育ちのため周りから疎んじられている。 |
| 北条 政村 |
連署(執権の補佐役)。長時の伯父。 |
| 宗尊 親王 |
鎌倉幕府6代将軍。16歳。 |
| 北条 時頼 |
鎌倉幕府5代執権。執権職を長時に譲ると出家し「道崇」と号す。 |
| 北条 滋子 |
鎌倉で暮らす実時の正室。政村の娘。産後の肥立ちが悪く精神が不安定。 |
| 北条 顕時 |
実時の長子。小侍所別当。 |
| 北条 六郎 |
実時の次子。もうすぐ元服。後の「北条 実政」。 |
| 太郎 |
金沢郷の百姓の子供。 |
| 三郎 |
金沢郷の百姓の子供。太郎の弟。 |
| みい |
金沢郷の百姓の子供。太郎・三郎の妹。 |
| 雪 |
鎌倉の実時邸での摩利伽の世話役。15歳。 |
| 姫大神 |
鶴岡八幡宮に祀られている女神。比売神。 |
| かなえ |
現世での摩利伽の友人。 |
| 鎌田 |
現世での摩利伽の高校の先輩。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
小室春斎は関東代官・榊原小兵衛に剣の腕を見込まれ、関東取締出役として関八州を廻村しながら治安を維持することを命ぜられていた。そのため彼のことを「八州廻り浪人奉行」と呼ぶ者も少なくなかった。そんな彼が藤沢に近い村の庄屋一家殺しを調べている中で、一人の男の子・正吉と出会った。鎌倉十二所の集落に住む正吉も賊に襲われ両親を殺されたというのだが、どうやら二つの事件の首謀者たちが同じということがわかった…。
|
|
| 作品の舞台 |
源氏山・・・春斎は又七から「九尾の作兵衛」に似た男たちを見たと聞きだします。
梶原・・・春斎は正吉を梶原庄の百姓の家で休ませます。
海蔵寺・・・春斎は鎌倉に入ると、海蔵寺に滞在します。
十二所・・・正吉の家があります。
光触寺・・・正吉は寺の門前で四人の目つきの悪い男たちとすれ違います。
極楽寺坂・・・萩乃を追いかけてきた利三郎は極楽寺坂の茶店に立ち寄ります。
|
|
| 登場人物 |
| 小室 春斎 |
「八州廻り浪人奉行」と呼ばれる関東取締出役。 |
| 榊原小兵衛 |
春斎を差配する関東代官。剣の腕を見込んで春斎を手代に起用する。 |
| 青野利三郎 |
駿河台下錦小路に住む幕府の小姓組の旗本。 |
| 萩乃 |
利三郎の妻。 |
| お常 |
萩乃の母。本石町の煙草問屋「井筒屋」の女将。 |
| 英吉 |
「井筒屋」の小者。 |
| 与市 |
青野家の中間。 |
| お道 |
青野家の下女。 |
| 島村長一郎 |
幕府の小姓組の旗本。利三郎の友人。 |
| 島村礼二郎 |
長一郎の弟。萩乃に言い寄る素浪人。 |
| 小田 孝蔵 |
礼二郎の仲間。 |
| 源蔵 |
礼二郎の仲間。 |
| 陽之助 |
礼二郎の仲間。 |
| 久平次 |
礼二郎の仲間。 |
| 貝塚善一郎 |
幕府の小姓組の旗本。 |
| 正吉 |
鎌倉十二所の百姓の子供。9歳。両親を殺した賊を探すため春斎に付いてまわる。 |
| 庄助 |
正吉の亡父。賊に斬られる。 |
| おたみ |
正吉の亡母。賊に手籠めにされ、首を絞められる。 |
| 良治 |
十二所の集落の名主。 |
| 道慶 |
海蔵寺住職。 |
| 円秀尼 |
東慶寺の寺務をつとめる尼。 |
| 作兵衛 |
浮浪人。「九尾の作兵衛」と呼ばれる悪党。 |
| 太助 |
作兵衛の仲間。 |
| 甚六 |
作兵衛の仲間。 |
| 老夫婦 |
小間物問屋「叶屋」の主人。 |
| 当八 |
藤沢宿の駕籠かき。 |
| 安吉 |
藤沢宿の駕籠かき。 |
| 精吉 |
江ノ島へ行く旅人。江戸の店者。 |
| 又七 |
藤沢弥勒寺村の百姓。 |
| 老婆 |
極楽寺坂の茶店の老婆。 |
| 亀蔵 |
逗子小坪に住む老人。 |
| おさと |
亀蔵の女房。 |
| 留吉 |
名越の畳屋。 |
| 娘 |
逗子小坪の飯屋の娘。 |
| 女中 |
居酒屋の女中。 |
|
| . |
 |
| 付添い屋六平太 玄武の巻 駆込み女 |
金子成人 |
小学館文庫 |
|
あらすじ
主に用心棒などを行う「付添い屋」の元・十河藩士の秋月六平太は、口入れ屋の忠七から東慶寺に駆け込む味噌問屋の内儀・お栄の付添いを依頼された。お栄は夫で店主の伊吉から受ける仕打ちに耐えかねて離縁を決意したというのだが、六平太は彼女から違和感を感じていた…。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・お栄は離縁をするために、六平太とともに東慶寺へ向かいます。
小袋谷・・・六平太は地元の百姓に、東慶寺への道筋を尋ねます。
鶴岡八幡宮・・・清七とお栄が参詣します。
|
|
| 登場人物 |
| 秋月六平太 |
浅草元鳥越に住む元信州十河藩の供番(ボディーガード)。「付添い屋」稼業を営む。 |
| 佐和 |
六平太の義妹。 |
| おりき |
小日向水道町の髪結い。六平太の情婦。 |
| おはん |
板橋の飲み屋の女。元・六平太の情婦。 |
| 穏蔵 |
おはんと六平太の子。八王子のお蚕屋に預けている。 |
| 園田 勘七 |
信州十河藩士。元・勘定方。六平太の幼馴染。 |
| 宮津太郎左衛門 |
信州十河藩国家老。 |
| 石川 頼母 |
信州十河藩中老。 |
| 小松新左衛門 |
信州十河藩江戸留守居役。 |
| 松村彦四郎 |
信州十河藩江戸家老。頼母の義兄。 |
| 忠七 |
神田岩本町の口入れ屋「もみじ庵」の主人。六平太に仕事を仲介する。 |
| 矢島新九郎 |
北町奉行所同心。六平太の知人。 |
| 作蔵 |
雑司ヶ谷の竹細工師。 |
| 弥吉 |
作蔵の倅。 |
| 菊次 |
作蔵の弟子。音羽の目明しの手下。六平太の知人。 |
| 音吉 |
浅草十番組「ち組」の纏持ち。市兵衛店の住人。 |
| おきみ |
音吉の娘。市兵衛店の住人。 |
| 留吉 |
大工。市兵衛店の住人。 |
| 下駄屋のおかみ |
市兵衛店の住人。 |
| 藤蔵 |
日本橋神田の目明かし。六平太の知人。 |
| 権助 |
本郷の目明かし。 |
| 森嘉屋伊吉 |
本郷の味噌問屋「森嘉屋」の主人。日本橋豆問屋の三男だが、「森嘉屋」に養子に入る。 |
| お栄 |
「森嘉屋」の内儀。元・奉公人。 |
| 清七 |
「森嘉屋」の手代。27~8歳。 |
| 飛騨屋山左衛門 |
木場の材木商「飛騨屋」の主人。 |
| おかね |
「飛騨屋」の内儀。 |
| お登世 |
「飛騨屋」の娘。 |
| お杉 |
日暮里の菓子商「錦月」女将。 |
| お鶴 |
杉の娘。 |
| 甘栄堂嘉兵衛 |
神田の菓子商「甘栄堂」の主人。 |
| 作太郎 |
嘉兵衛の倅。 |
| 倉橋兵庫之介 |
嘉兵衛の用心棒。 |
| 椿屋杢兵衛 |
東慶寺の門前宿「椿屋」の主人。 |
| 番頭 |
「椿屋」の番頭。 |
| 鈴 |
「島田屋」の新造。19歳。「椿屋」で滞在中。 |
| 島田屋利一郎 |
「島田屋」の主人。 |
| 三吉 |
「島田屋」に頼まれた渡世人。薄眉の男。 |
| 百姓 |
鎌倉小袋谷の百姓。 |
|
| . |
 |
| 北の伝承 義経北行伝説を行く |
大曲隆毅 |
VIMAGIC
BOOKS |
|
あらすじ
衣川で討たれた義経の歴史と異なり、平泉で討たれず北へ逃げたという伝説も未だに語り継がれている。そこでその伝説を辿っていこうと思う…。
|
|
| 作品の舞台 |
腰越・・・景時と義盛は腰越の浜で義経の首実検をします。
|
|
| 登場人物 |
| 源 義経 |
源氏の御曹司。頼朝の異母弟。 |
| 武蔵坊弁慶 |
義経の郎党。怪力の破壊僧。 |
| 常陸坊海尊 |
義経の郎党。 |
| 佐藤 継信 |
義経の郎党。元・藤原氏家臣。 |
| 佐藤 忠信 |
義経の郎党。元・藤原氏家臣。継信の弟。 |
| 鈴木三郎重家 |
義経の郎党。 |
| 亀井六郎重清 |
義経の郎党。重家の弟。 |
| 鷲尾三郎常春 |
義経の郎党。 |
| 杉目小太郎 |
義経の郎党。義経の影武者。 |
| 板橋 長治 |
義経の郎党。 |
| 喜三太 |
義経の郎党。 |
| 河田 次郎 |
義経の郎党。 |
| 静御前 |
義経の愛妾。白拍子。 |
| 磯禅師 |
静の母。白拍子。 |
| 浄瑠璃姫 |
義経の愛妾。三河国生まれ。 |
| 久我太郎娘 |
義経の妻。公家の娘。 |
| 権之守 |
重家・重清の乳母。 |
| 藤原 秀衡 |
奥州藤原氏3代当主。 |
| 藤原 泰衡 |
奥州藤原氏4代当主。秀衡の次男で嫡男。 |
| 藤原 秀栄 |
十三湊福島城主。秀衡の弟。 |
| 藤原 基成 |
民部少輔。 |
| 阿部 七郎 |
八戸の豪族の息子。 |
| 関 諄甫 |
八戸藩の儒医。 |
| 榊 浄円 |
義経の郎党の子孫。 |
| 和田 義盛 |
鎌倉幕府御家人。侍所別当。 |
| 梶原 景時 |
鎌倉幕府御家人。侍所所司。 |
| シタカベ |
江差・鴎島に住むアイヌの酋長。 |
| フキミ |
シタカベの娘。 |
| ジンギス・ハーン |
大蒙古の国王。 |
| フビライ・ハーン |
大蒙古の国王。ジンギスの孫。 |
| マルコ・ポーロ |
イタリアの商人。フビライに17年間仕える。 |
|
| . |
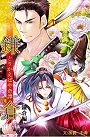 |
| 鎌倉とりかえばや奇譚 第二部 鎌倉編 |
加賀千寿 |
ルナテーラ
ブックス |
|
あらすじ
朝廷を手を組み幕府を倒すために鎌倉へやってきた紗月だったが、幕府の有力御家人・平賀義信の養女「千鶴」として女装をさせられながらも、母の実家である北条家を毛嫌いする将軍・源頼家に会うことができた。一方、紗月と瓜二つの娘・千鶴は紗月の影武者として武蔵国畠山庄に残っていたが、領主・畠山重忠親子と共に鎌倉にある御所へ出向くことになった。果たして二人は幕府の中枢に近づくことができるのだろうか…。
|
|
| 作品の舞台 |
由比ガ浜・・・畠山重康の館があります。
鶴岡八幡宮・・・紗月は静御前の子として、舞殿で舞を披露します。 |
|
| 登場人物 |
| 紗月 |
源義経と静御前の子。朝廷と手を組み北条家が動かす幕府を倒そうとしている。 |
| 千鶴 |
紗月と瓜二つの娘。上野国の小さな村の出。紗月の影武者をつとめるが、妾でもある。 |
| 炎岳 |
紗月の郎党。薙刀の遣い手で陰陽師。 |
| 下田小五郎 |
紗月の郎党。 |
| 尾根 弥六 |
紗月の郎党。 |
| 水木 |
紗月の乳母。 |
| 舞衣 |
紗月と千鶴の娘。 |
| 源 頼家 |
鎌倉幕府二代将軍。母の実家でもある北条家をよく思っていない。 |
| 千幡 |
頼家の弟。後の「源実朝」。 |
| 一幡 |
頼家の子。 |
| 北条 政子 |
頼家の母。尼御台。頼家より千幡を可愛がる。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。言うことを聞かない頼家を排除しようとしている。 |
| 北条 義時 |
時政の息子。有力な御家人。 |
| 比企 能員 |
有力な御家人。頼家の舅。 |
| 比企 三郎 |
有力な御家人。能員の子。 |
| 畠山 重忠 |
有力な御家人。武蔵国畠山庄の領主。 |
| 畠山 重保 |
有力な御家人。重忠の子。千鶴に気がある。 |
| 平賀 義信 |
有力な御家人。 |
| 小糸 |
平賀家の侍女。20歳過ぎ。 |
| 後鳥羽院 |
朝廷の権力者。 |
| 門番 |
重保の館の門番。中年男。 |
|
| . |
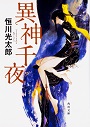 |
|
あらすじ
鎌倉の山中で庵を結ぶ遼慶は、一人の男と出会った。「仁風」という名の彼は、日本人でありながら蒙古軍の潜入部隊の一員として博多に上陸した過去の話を語りだした…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・人里離れた山の裾野に遼慶の庵があります。
|
|
| 登場人物 |
| 仁風 |
南宋の商人の養子。捕縛後に蒙古(大元)軍の潜入部隊として日本に上陸する。対馬の農家の四男坊。 |
| 陳 |
仁風の養父。南宋の商人。 |
| 楊 |
仁風の先輩船員。蒙古軍に捕縛される。 |
| 謝太郎国明 |
博多にある中国人街「大唐街」を牛耳る豪商。人情家。 |
| 孫娘 |
国明の孫娘。 |
| 安平 |
蒙古軍の博多潜入部隊「旅楽隊」の隊長。30歳代半ば。 |
| 紀千 |
「旅楽隊」の副隊長。 |
| 鈴華 |
「旅楽隊」の女性隊員。巫術師。 |
| リリウ |
鈴華が飼う鼬。 |
| クビライ |
大元王朝の皇帝。 |
| 忽敦 |
大元軍の総司令官。 |
| 北条 時宗 |
鎌倉幕府8代執権。 |
| 遼慶 |
元・僧侶。還俗し鎌倉の山中で庵を結ぶ。 |
|
|
  |