| . |
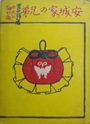 |
|
あらすじ
男5人・女2人の7人兄弟の安城家の四男・加島昌造は、沖津の待合に芸妓や幇間、遊び仲間たちを呼んではどんちゃん騒ぎを繰り返す放蕩三昧の作家だ。そんな彼の長兄・安城文吉が雑誌記者の萩原敏子と一緒に失踪してしまった。2人を心配する兄弟や家族、仕事仲間たち。しかし2人は軽井沢の別荘で縊死死体となって発見された…。
|
|
|
| 作品の舞台 |
極楽寺・・・壬之助が静養する安城寺家の別荘があります。
扇ガ谷・・・昌造は作品を書くために旅館「清風園」に数日間逗留します。
雪ノ下・・・三勝が経営する料理屋兼旅館「三勝茶屋」があります。
七里ガ浜・・・文吉と昌造が砂浜を歩きながら語り合います。 |
|
| 登場人物 |
| 安城 文吉 |
安城家の長男。作家。番町の本家に住む。 |
| 堀内 綾子 |
安城家の長女。堀内家に嫁ぐ。 |
| 安城壬之助 |
安城家の次男。鎌倉・極楽寺の別荘で静養中。 |
| 藤井萬喜子 |
安城家の次女。藤井家に嫁ぐ。 |
| 吉井 健吉 |
安城家の三男。新橋に勤める会社員。父方の祖母の生家で薩摩藩・吉井家を継ぐ。 |
| 加島 昌造 |
安城家の四男。放蕩作家。母の生家で南部藩・加島家を継ぐ。逗子市新宿に住む。 |
| 安城 隼夫 |
安城家の五男で末子。 |
| 安城 道夫 |
文吉の長男。 |
| 安城 信吉 |
文吉の次男。 |
| 安城 健三 |
文吉の三男。 |
| 安城茂登子 |
壬之助の妻。 |
| 安城八重子 |
壬之助の長女。 |
| おしげ |
昌造の現在(2番目)の妻。 |
| 春江 |
昌造の元妻。 |
| わか子 |
春江の妹。 |
| 加島 昌一 |
昌造の長男。 |
| 加島 欽造 |
昌造の次男。 |
| 加島 裕子 |
昌造の長女。 |
| 加島 敏三 |
昌造の三男で末子。 |
| 母 |
7兄妹の母。熱海の別荘で隠居生活。 |
| 安城 謙介 |
7兄妹の遠縁。分家筋。 |
| 松 |
加島家の女中。 |
| 萩原 敏子 |
文吉の愛人。出版社「女性主潮社」の記者。 |
| 萩原 親敦 |
敏子の夫。保険協会の理事。 |
| 落合 光恵 |
文吉の愛人。 |
| 久保 |
昌造の作家仲間で高校時代の友人。 |
| 北 繍太郎 |
昌造の作家仲間。先輩作家。 |
| 畠山 |
昌造の作家仲間。昌造と同年代。 |
| 宇田川 |
昌造の作家仲間。 |
| 井口 |
昌造の作家仲間。 |
| 高松 |
昌造の作家仲間。 |
| 小野 |
昌造の作家仲間。 |
| 河津 |
昌造の作家仲間。 |
| 小野田 |
昌造の作家仲間。 |
| 阪本三千子 |
昌造の作家仲間。 |
| 瑛龍 |
昌造の遊び仲間。芸妓。 |
| 三平 |
昌造の遊び仲間。幇間。 |
| お民 |
昌造の遊び仲間。沖津の待合の女将。 |
| 歌川 |
昌造の遊び仲間。 |
| 貞城 |
昌造の遊び仲間。講釈師。 |
| 市川 鰕蔵 |
昌造の遊び仲間。歌舞伎役者。 |
| 三谷 |
昌造の遊び仲間。劇作家。 |
| 川崎 |
昌造の遊び仲間。若い歌舞伎役者。 |
| 村瀬 |
昌造の遊び仲間。日本書家。 |
| 佐山 俊次 |
昌造の遊び仲間。「日本劇場」支配人秘書。元・作家。 |
| 西山 普烈 |
昌造の書斎に通う混血児の不良青年。 |
| 武宮 |
西山の知人。昌造の書斎に西山と通う。 |
| 勝彌 |
瑛龍の朋輩。若い芸妓。 |
| 小なみ |
瑛龍の朋輩。若い芸妓。 |
| 丸二の兄 |
瑛龍の下働き。 |
| おこう |
芸妓。有名な芸者家・間倉家の養女。 |
| お富 |
芸妓。 |
| 鈴香 |
芸妓。 |
| 鶴代 |
芸妓。 |
| 愛香 |
芸妓。 |
| お梅 |
芸妓。 |
| お蘭 |
芸妓。お梅の妹。 |
| 三勝 |
鎌倉・雪ノ下にある「三勝茶屋」の女将。元・芸妓。 |
| お圭 |
料理屋「美登利家」の女将の娘。 |
| お雪 |
鎌倉・扇ガ谷にある旅館「清風園」の女中。 |
| 澤田 |
日本橋の待合「松川家」の元女将。 |
| お鐵 |
盲目の女按摩。 |
| 田代 |
神戸に住む文吉の親友。 |
| 廣田 |
文吉の親友。 |
| 太田 |
文吉を翻意にしていた出版社社長。 |
| 加茂 貫治 |
文吉の知人。出版社「文化堂」の主人。 |
| 岩佐男爵夫人 |
敏子の友人。 |
| 根津 |
軽井沢にある安城家の別荘の管理人。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
私が子どもの頃の鎌倉は東京から汽車で2時間ほどかかり、駅前広場も今の半分ほどの広さしかなく、長谷の曲り角あたりは人家もなく水田や蓮田が広がっていました…。
|
|
| 作品の舞台 |
材木座・・・大蔵省の上司と喧嘩した父は、材木座の別荘に行き失意の時代を過ごしました。
|
|
| 登場人物 |
| 里見 弴 |
物語の語り手。小説家。 |
| 有島 武郎 |
弴の長兄。小説家。 |
| 有島 生馬 |
弴の次兄。画家。 |
| 有島 隆三 |
弴の三兄。 |
| 有島 愛子 |
弴の長姉。 |
| 有島志摩子 |
弴の次姉。 |
| 勝見 |
有島家のかかりつけの医師。 |
| 孫次郎 |
有島家に出入りする大工。 |
| 柳谷 午郎 |
弴の友人。「睦友会」の文士仲間。 |
| お末 |
午郎の妹。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
7人兄妹の6番目にあたる天野吉は父方が薩摩藩、母方は南部藩の出てあるものの、働き盛りの年頃になると家のトラブルに巻き込まれて人生の転換を迫られた…。
|
|
| 作品の舞台 |
滑川・・・滑川河口の近くに文吉の別荘があります。
|
|
| 登場人物 |
| 天野 吉 |
文吉の娘。7人兄妹の6番目。南部藩主の室・明子の小姓。 |
| 天野 文吉 |
吉の父。上司とこじれ退職後、鎌倉の別荘で隠棲。 |
| 天野 宏子 |
吉の母。 |
| 天野 武文 |
文吉の亡父。薩摩藩士。家内騒動の責任をとり遠島の身のまま死亡。 |
| 加島判左衛門宏邦 |
宏子の亡父。南部藩江戸留守居役。 |
| 加島 志津 |
宏子の亡母。久留米藩士・今井九一郎の次女。 |
| 加島 宏光 |
宏子の亡弟。大阪府収税部検閲課長。 |
| 加島 宏紹 |
宏光の養子。 |
| 命尾 寿六 |
父の友人。謡曲の師。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鎌倉に本宅を持つ小説家の晋策は、番町に妾・お孝を囲っていたが都内への空襲が頻繁に行われるようになったので彼女を信州・植田に疎開させた。するとお孝は疎開先の近くに存在する「姥捨伝説」を知り、自分たちが捨てられるのではないかと心配になり、急にわがままを言いだした…。
|
|
|
|
| 登場人物 |
| 晋策 |
鎌倉に住む小説家。 |
| 妻 |
晋策の妻。 |
| 清雄 |
晋策の長男。 |
| 誠子 |
清雄の妻。 |
| 次男 |
晋策の次男。 |
| 都留 |
晋策の内弟子兼女中。 |
| お孝 |
晋策の妾。 |
| お春 |
晋策の妾宅のばあや。 |
| 母 |
都留の母。信州・別所の大百姓。 |
| 次男 |
都留の弟。次男。出征中。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
遠武家のご隠居・遠武まきは現在鎌倉に居を持つまきの四男・彌四郎の家族と悠々自適に暮らしている。戦況が悪化する中、彌四郎が単身赴任先の栃木に家族を疎開させたいと言いだし、自分に相談がなかったことでまきはへそを曲げ頑として動かないでいた。しかしまきは近頃物を食べるたびに胃が痛くなったことで医師に診てもらったところ、胃ガンにかかっていることを知らされる…。
|
|
| 作品の舞台 |
和田塚・・・遠武彌四郎の家があります。
建長寺・・・:建長寺の僧・Мからまきに手紙が届きます。
|
|
| 登場人物 |
| 遠武 まき |
鎌倉で彌四郎一家と暮らす遠武家のご隠居。彌介・彌四郎・美代子の母。鹿児島生まれ。 |
| 遠武 彌介 |
まきの亡長男。二百三高地で戦死。 |
| 遠武 健吉 |
彌介の長男。まきの孫。 |
| 遠武彌四郎 |
まきの四男。鎌倉に住むH鉱業の専務。現在、栃木に単身赴任中。 |
| 遠武 清子 |
彌四郎の妻。 |
| 長女 |
彌四郎の長女。15歳。高等女学校4年生。 |
| 次女 |
彌四郎の次女。10歳。国民学校5年生。 |
| 三女 |
彌四郎の三女。8歳。国民学校3年生。 |
| 遠武美代子 |
まきの長女。彌介・彌四郎の妹。 |
| М |
まきの知人。建長寺の僧。 |
| 堀内 |
彌四郎の友人。医師。 |
| 浅井 |
医師。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
無条件降伏後、サイパンに出征していたY・Yの消息が途絶え家族たちもあらゆる手を尽くしたが、全くわからないままだった。そして昭和22年末をもって全ての消息不明の出征者を「戦死者」とする御触れが出た。それでも父は納得できなかったが、昭和23年6月にY・Yの葬式を行なうことになった。故人の友人たちが集まる中、ベースボール好きだったYを想い、家族や参列者たちで野球の追悼試合することになった…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・Y・Yの生家があります。
北鎌倉・・・次男が新居を構えます。
|
|
| 登場人物 |
| Y・Y |
陸軍主計曹長。サイパンで戦死。父の長男。 |
| 父 |
Yの父。 |
| 母 |
Yの母。 |
| 長弟 |
Yの長弟。父の次男。 |
| 次弟 |
Yの次弟。父の三男。 |
| 長妹 |
Yの長妹。父の長女。茨城の他家に嫁ぐ。 |
| 夫 |
長妹の夫。 |
| 長女 |
長妹の長女。 |
| 長男 |
長妹の長男。 |
| T |
父の18歳年下の友人。 |
| N |
東京郊外に住む紳商。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
江の島の旅館の三男坊・倉持辰介は海産物の仕入れなどを手伝いながら島の若者として暮らしている。ある日島では見かけない派手な洋装の女性を見かけた辰介が声をかけると、彼女は軍需工場で辰介と一緒に働いていた千葉玉枝だった。彼女は海が見たいから島へやってきたようなので、辰介は登内を案内することにしたのだが…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・辰介は海産物を仕入れ鎌倉の料理屋に販売します。
|
|
| 登場人物 |
| 倉持 辰介 |
江の島の旅館兼料理屋「M楼」の三男坊。戦時中は藤沢の軍需工場の仕上工。 |
| 千葉 玉枝 |
島へ観光に来た女性。戦時中は藤沢の軍需工場の検査工。 |
| 堀川 花子 |
戦時中の辰介の情婦。 |
| 兄 |
藤沢市鵠沼に住む玉枝の兄。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
父の寵愛を一身に受けた長男のYは、関東大震災がおきたと同時にその家族の心が離れていく予感がした。父も徐々にいい作品が書けなくなり、Y自身も自立した生活を考えなければならないのだ。しかし彼の心配が解消されることがないまま、日本は戦争に突入してしまう…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・大震災で家を失ったYの一家は鎌倉へ避難します。
|
|
| 登場人物 |
| Y |
Y家の長男。五人兄妹の惣領。 |
| 父 |
Yの父。小説家。長男を溺愛する。 |
| 母 |
Yの母。内縁の妻。 |
| 亡姉 |
Yの亡姉。夭折。 |
| E |
Y家の次男。 |
| 妹 |
Y家の次女。 |
| 弟 |
Y家の三男。 |
| 書生 |
Y家の書生。大分生まれ。 |
| 同窓生 |
父の弟の同級生。銀行の支店長。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鎌倉に住む小説家の山内英夫は、大阪からの帰りの列車で席が一緒になった若い娘が鎌倉の病院へ見舞いに行くというので、鎌倉の駅から道案内までしてあげた。するとその翌日、その娘・浅妻が英夫の自宅を訪ね金を借りに来た…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・山内英夫邸や、浅妻の継母が入院する病院があります。
|
|
| 登場人物 |
| 山内 英夫 |
鎌倉に住む小説家。 |
| 妻 |
英夫の妻。 |
| 山内 静男 |
英夫の四男。 |
| 浅妻 |
英夫が帰鎌する列車に同乗した乗客。安っぽいワンピースを着た若い娘。 |
| 継母 |
浅妻の継母。 |
| 男 |
英夫が帰鎌する列車に同乗した乗客。雑誌記者。 |
| 女 |
英夫が帰鎌する列車に同乗した乗客。中流家庭の若奥様。 |
| O |
英夫の知人。興業界の元老。 |
| 警官 |
新宿・淀橋所の警官。 |
| 課長 |
鎌倉署の捜査課長。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
この頃の私は父の癖が移ってしまったのか、大して整った顔でもないのにやたらと手鏡で自分の顔を確認するようになった。そのためにわざわざ東京まで行って歯の治療をするほどなのだ。そんな治療の帰りの電車内で、私はある視線を感じた…。
|
|
|
|
| 登場人物 |
| 私 |
鎌倉に住む男性。 |
| 父 |
私の父。 |
| 岩本 素白 |
随筆家。 |
| 女性 |
横須賀線の女性客。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
題名を「かまくらのたにだに」と読まれると、若干実情と違ってくる。鎌倉は山と呼ぶほどの隆起もなく、逆に深い谷もない。丘と丘の間をいつしか「やと」「やつ」と呼ぶようになったのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
谷戸・・・鎌倉にはたくさんの谷戸があります。
|
|
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
郵便は「扇ガ谷○○番地」で届く我が家だが、役所の書類には「字泉ヶ谷」を付けないといけないらしい。「泉ヶ谷」の名の由来はおそらく鎌倉十井のひとつ・泉の井が近くにあるからだとは思うが、新たに引っ越してきた人たちにはわからない話である…。
|
|
|
|
| 登場人物 |
| 里見 弴 |
物語の語り手。小説家。 |
| 有島 武郎 |
弴の長兄。 |
| 有島 生馬 |
弴の次兄。 |
| A |
里見弴邸の前の住人。 |
| N |
Aの旧友。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
夏目漱石の作品「門」と円覚寺塔頭「帰源院」との繋がりは、私が思っている以上に知られていない。半世紀近く湘南の地で過ごし、作品に興味をもっていた私だから知っていることなのかもしれない…。
|
|
| 作品の舞台 |
円覚寺・・・夏目漱石の「門」の舞台となりました。
|
|
| 登場人物 |
| 里見 弴 |
物語の語り手。小説家。 |
| 夏目 漱石 |
小説家。 |
| 鈴木 大拙 |
哲学者。 |
| 島崎 藤村 |
小説家。 |
|
|
  |