| . |
 |
鞍馬天狗御用盗異聞
奇怪な覆面武士の巻 |
大佛次郎 |
博文館 |
|
あらすじ
江戸・三田にある薩摩藩江戸屋敷では、益満休之助が京から江戸へ向かう御用盗・鞍馬天狗一行を待ちわびていた。薩摩藩は彼らを使い討幕のきっかけとなる騒ぎを起こそうとしているのだ。そんな彼のもとに江戸へ向かう御用盗の一味・天草則武が斬られたという知らせが入った…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・鞍馬天狗は正体を見破られないように鎌倉から来たと嘘をつきます。
|
|
| 登場人物 |
| 鞍馬天狗 |
京で活躍する勤王の志士。 |
| 天草 則武 |
鞍馬天狗らと共に薩摩屋敷へ向かう御用盗。 |
| 隼の三吉 |
鞍馬天狗らと共に薩摩屋敷へ向かう御用盗。 |
| 夜桜のお辰 |
鞍馬天狗らと共に薩摩屋敷へ向かう御用盗。 |
| 黒姫の吉兵衛 |
鞍馬天狗らと共に薩摩屋敷へ向かう御用盗。 |
| 西郷吉之助 |
薩摩藩の重臣。 |
| 伊牟田尚平 |
薩摩藩士。 |
| 益満休之助 |
薩摩藩士。 |
| 権田 |
薩摩藩士。 |
| 小島 |
薩摩藩士。 |
| 落合 |
薩摩藩士。 |
| 平野次郎国臣 |
攘夷派志士。 |
| 田中河内介 |
攘夷派志士。 |
| 安積 五郎 |
攘夷派志士。 |
| 清河 八郎 |
攘夷派志士。 |
| 小野 宗房 |
公家。 |
| 老婆 |
丸子橋辺りに住む老婆。 |
|
| . |
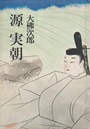 |
|
あらすじ
初代執権となった北条時政は、若い後妻の牧の方のわがままを理由に他の御家人たちを巻き込んだ横暴さが徐々に露呈してきた。次男で有力御家人の北条義時は、父との戦いを決意し周りの御家人たちも戦の準備をしている。父と弟の争いを心配する政子は、息子で3代将軍の源実朝に仲裁を頼もうとするのだが、、彼は和歌のことで頭がいっぱいだった…。
|
|
| 作品の舞台 |
小町・・・北条義時の館があります。
名越・・・北条時政の館があります。
夷堂橋・・・戦に向かう鎧武者が次第に増えます。
由比ガ浜・・・和田一族の首級を集めます。
鶴岡八幡宮・・・公暁が実朝を暗殺します。
|
|
| 登場人物 |
| 源 実朝 |
鎌倉幕府3代将軍。14歳。政子の次男。頼朝の四男。政より和歌に夢中。 |
| 北条 政子 |
実朝の母。頼朝の妻。時政の長女。尼将軍。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。故人。政子の亡夫。頼家・実朝の亡父。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。政子・義時・阿波局・時房の父。名越の御所に暮らす。 |
| 北条 義時 |
時政の次男。後の鎌倉幕府2代執権。政子の同母弟。阿波局の同母兄。時房の異母兄。相模守。 |
| 阿波局 |
時政の次女。実朝の乳母。政子・義時の同母妹。時房の異母姉。全成の妻。 |
| 北条 時房 |
時政の三男。政子・義時・阿波局の異母弟。後の鎌倉幕府初代連署。 |
| 北条 泰時 |
義時の嫡男。後の鎌倉幕府3代執権。 |
| 阿野 全成 |
阿波局の夫。実朝の乳母夫。故人。 |
| 源 頼家 |
鎌倉幕府2代将軍。故人。頼朝の次男。実朝の同母兄。修善寺で斬死。 |
| 一幡 |
頼家の長男。故人。比企の乱で死亡。 |
| 公暁 |
頼家の次男。後に実朝の猶子。鶴岡八幡宮別当。阿闍梨。幼名・善哉。 |
| 比企 能員 |
幕府の有力御家人。故人。頼家の乳母夫で舅。 |
| 畠山 重忠 |
幕府の有力御家人。故人。時政の娘婿。鎌倉武士の鑑。 |
| 畠山六郎重保 |
幕府の御家人。故人。重忠の嫡男。 |
| 畠山 重慶 |
重忠の遺児。日光山別当。 |
| 稲毛入道重成 |
幕府の御家人。故人。時政の娘婿。 |
| 御台所 |
実朝の正妻。坊門家の姫。 |
| 坊門 忠信 |
御台所の兄。公卿。大納言。 |
| 兵衛尉清綱 |
御台所付きの侍。 |
| 牧の方 |
時政の後妻。 |
| 牧 宗親 |
幕府の御家人。牧の方の父。 |
| 平賀 朝雅 |
牧の方の娘婿。京都守護。 |
| 和田左衛門尉義盛 |
幕府の有力御家人。侍所別当。 |
| 和田新左衛門尉常盛 |
幕府の御家人。義盛の嫡男。 |
| 朝夷名三郎義秀 |
幕府の御家人。義盛の三男。 |
| 和田四郎左衛門尉義直 |
幕府の御家人。義盛の四男。 |
| 和田六郎兵衛尉義重 |
幕府の御家人。義盛の五男。 |
| 和田 義信 |
幕府の御家人。義盛の六男。 |
| 和田 秀盛 |
幕府の御家人。義盛の七男。 |
| 和田新兵衛尉朝盛 |
幕府の御家人。常盛の長男。義盛の孫。 |
| 和田平太胤長 |
幕府の御家人。義盛の甥。 |
| 三浦兵衛尉義村 |
幕府の有力御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 足達九郎右衛門尉景盛 |
幕府の有力御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 足利上総三郎義氏 |
幕府の有力御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 長沼五郎宗政 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 結城七郎朝光 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 天野六郎政景 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 金窪兵衛尉行親 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 安東次郎忠家 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 津々見刑部丞忠季 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 宮内兵衛尉公氏 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 佐々木五郎義清 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 江戸左衛門尉能範 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 源近江守頼茂 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 三浦五郎三郎 |
幕府の御家人。和田合戦では北条勢。 |
| 深見三郎次郎致興 |
幕府の御家人。義時の家臣。和田合戦では北条勢。 |
| 東平太重胤 |
幕府の御家人。実朝の近侍。和田合戦では北条勢。 |
| 土屋大学助義清 |
幕府の御家人。和田合戦では和田勢。 |
| 古郡左衛門尉保忠 |
幕府の御家人。和田合戦では和田勢。 |
| 渋谷次郎高重 |
幕府の御家人。和田合戦では和田勢。 |
| 中山四郎重政 |
幕府の御家人。和田合戦では和田勢。 |
| 深沢三郎景家 |
幕府の御家人。和田合戦では和田勢。 |
| 横山馬允時兼 |
幕府の御家人。横山党。和田合戦では和田勢。 |
| 大江大膳太夫広元 |
幕府の官吏。政所別当。 |
| 二階堂山城判官行村 |
幕府の官吏。 |
| 佐奈田与一 |
頼朝勢の侍。故人。 |
| 泉小次郎親平 |
信濃国の御家人。 |
| 鴨 長明 |
名高い歌人。 |
| 藤原 定家 |
今日で高名な歌人。 |
| 藤原左金吾基俊 |
歌人。 |
| 内藤右馬允知親 |
歌人。 |
| 源 仲章 |
実朝の侍読。文章博士。 |
| 明恵上人 |
華厳僧。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
海軍会計士官だった守屋恭吾は、上司や同僚の汚職の責任を一人で被り引責辞任、存在を消されてしまった。そこで彼は自身の博才も手伝って日本に妻子を残したまま世界各地を放浪した。やがて中国人に成りすましてシンガポールにいた恭吾は、昔の仲間だった牛木利貞と出会い、現地で料亭を経営する若い女将・高野左衛子を紹介される…。
|
|
| 作品の舞台 |
山ノ内・・・牛木利貞邸があります。
円覚寺・・・利貞と恭吾は境内を散策しながら過去を語り合います。
|
|
| 登場人物 |
| 守屋 恭吾 |
元・海軍会計士官のエリート将校。汚職の責任を一人で被り引責辞任。放浪の身となる。 |
| 守屋 伴子 |
恭吾の娘。雑誌社「エトワール社」の記者。洋裁の仕事もしている。 |
| 隠岐 節子 |
恭吾の元妻。伴子の母。達三と再婚。 |
| 隠岐 達三 |
節子の夫。元・大学教授。 |
| 牛木 利貞 |
海軍大佐→海軍少将。北鎌倉に住む。 |
| 息子 |
牛木の亡息。ミッドウェイで戦死。享年23歳。 |
| 高野左衛子 |
シンガポールに住む料亭の女将。30歳。海軍将校たちを手玉に取る。 |
| 小野崎公平 |
放浪の画家。49歳。日本に帰国後はキャバレーのボーイ。 |
| アブドラ |
左衛子の運転手。マレー人。 |
| 今西 |
若い海軍将校。中尉。牛木の部下。帝国大学卒業。 |
| 岡村 俊樹 |
左衛子の甥。23歳。P大学の学生。 |
| 藤原 |
西銀座にある古書店の主人。 |
| 岡部 雄吉 |
古書店のアルバイト。言語学専攻の大学生。 |
| ヘレン水町 |
浅草の踊り子。 |
| 美津 |
キャバレーのホステス。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
私が住む鎌倉では季節によって色々な光景が見られ、また友人や知人たちとの出会いや別れも多々あった。そういったことを書いていこうと思う・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
泉ガ谷・・・亀田輝時邸があります。
海蔵寺・・・底抜の井があります。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 亀田 輝時 |
泉ガ谷に住む郷土史家。53歳。 |
| 亀田 輝朝 |
輝時の息子。2歳。 |
| K |
次郎の友人。 |
| 弟 |
Kの弟。会社員。 |
| 和田日出吉 |
次郎の旧友。新聞社の編集者。 |
| 猪熊弦一郎 |
新制作協会派の画家。 |
| 佐藤 敬 |
新制作協会派の画家。 |
| 小磯 良平 |
新制作協会派の画家。 |
| 脇田 和 |
新制作協会派の画家。 |
| 吉川幸次郎 |
京都大学教授。 |
| 加藤 武雄 |
小説家。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鎌倉住まいの私にとって、三輪車で家の近所まで売りに来てくれる豆腐屋が作る豆腐がうまくて誇らしい。都内からやってくる友人たちも、寺の門前にある豆腐屋はうまい豆腐を作ると評判が良い。ただ近頃は、豆から手づくりされる豆腐が少なくなり、大量の豆の粉から作るものが増え、本当の豆腐の味が消えようとしているのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・都内から来る友人たちにも鎌倉の豆腐は美味いと言われます。
|
|
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
歌舞伎に詳しい遠藤為春さんが大船の病院で亡くなった。彼の死によりもう歌舞伎界の指揮者はほとんどいなくなってしまうことは、ファンにとっても悲しいことだろう…。
|
|
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 遠藤 為春 |
歌舞伎研究家。 |
| 高橋誠一郎 |
浮世画研究家。 |
| 鏑木 清方 |
洋画家。 |
| 正宗 白鳥 |
歌舞伎通の小説家。 |
| 安藤 鶴夫 |
歌舞伎通の小説家。 |
| 9代目市川團十郎 |
歌舞伎役者。 |
| 尾上多賀之丞 |
歌舞伎役者。 |
| 大谷竹次郎 |
実業家。「松竹」の創始者。 |
| 女将 |
新橋の料亭「菊村」の女将。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
妻の手術が5時間ほどかかると言われ、私は近くにある銭洗弁天へ行ってみた。かれこれ20年ぶりに訪ねたのだが、境内はほどよく参拝客でにぎわい、茶店で飲むビールも美味く谷戸に吹く風も心地よかった…。
|
|
| 作品の舞台 |
銭洗弁財天宇賀福神社・・・次郎は20年ぶりに訪ねます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 野尻 登里 |
次郎の妻。入院中。 |
| 女将 |
銭洗弁天の参拝客。小料理屋の女将。 |
| 若者 |
銭洗弁天の参拝客。若い女性。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鎌倉はこの時期になると梅の花が満開になる。この時期になると私は右大臣・源実朝を思い合わせる…。
|
|
| 作品の舞台 |
瑞泉寺・・・梅の花が見事に咲きます。
覚園寺・・・梅の花が見事に咲きます。
鶴岡八幡宮・・・源実朝が公暁に暗殺されます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 鏑木 清方 |
洋画家。 |
| 妻 |
清方の亡妻。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
私は鎌倉まつりで行なわれる「静御前コンテスト」の審査委員長を依頼された。そもそも「御前」という呼称は有夫の女性に対するものなのだが、いざコンテスト会場へ行ってみると若い女性ばかりが並び、中には14歳の女の子が2人もいるのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・次郎は鎌倉まつりのミスコンテストの審査委員長を頼まれます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 静御前 |
今日の白拍子。義経の愛妾。 |
| 源 頼朝 |
源氏の棟梁。鎌倉殿。 |
| 源 義経 |
頼朝の異母弟。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
書斎の窓から外を眺めていた私はふと水の音が聴きたくなって外へ出てみた。昔は滑川沿いの道を歩いていると、木の枝をくぐるせせらぎの音が聞こえていたのだが、今ではコンクリートの蓋がかぶせられ、さらに自動車の音で水の音がかき消されてしまっているのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
滑川・・・昔は心地よいせせらぎの音が聞こえていました。
|
|
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
私が暮らす鎌倉市は、観光シーズンになると道路に自動車の列が城壁のように並ぶ。みんな旅に出たいという気持ちになるのだろう。そもそも庶民が旅に出るようになった原因の一つに、住居が家らしい落ち着きを失ったこともあるのだと思う。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・観光シーズンになると混雑が激しくなります。
|
|
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
朝起きたら新聞に瑞泉寺の大下豊道和尚がタヌキを捕まえた写真が載っていた。和尚も「寺なので殺生して食べるわけにはいかない」と冗談交じりにコメントしていた。生かしてペットとして飼えば、何か役に立つのではないかと私は考えた。山中の寂しい場所にあるお寺なので、タヌキに美しい女性に化けてもらうのはどうだろう…。
|
|
| 作品の舞台 |
瑞泉寺・・・豊道和尚がタヌキを捕まえます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 大下 豊道 |
瑞泉寺第28世和尚。 |
| 今道 潤三 |
東京放送専務。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
私の家から出歩ける範囲で一番見事な桜の木は、鎌倉山の常盤山文庫にある桜だろう。植えてから30年ほどの若木だが、日当たりが良いので自由で伸びやかな枝ぶりをしている…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉山・・・常盤山文庫に見事な桜の木があります。
|
|
|
|
| . |
 |
|
あらすじ
明月院の紫陽花を見に行きたいのだが、毎年その時期になると忙しいことにかまけて行けずじまいでいる。寺が埋まるほど花が咲き誇り、その鞠のような花冠を見せる姿は、独特な景色で夏の夕方の詩となっている…。
|
|
| 作品の舞台 |
明月院・・・次郎はなかなか紫陽花の時期に訪ねることができずにいます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 松本 恵子 |
翻訳家・エッセイスト・推理作家。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
私はひそかに「鎌倉びと」と呼んでいる人間の種族がいる。昔の鎌倉に住む住人といえば、病身で療養に来ている者や、勤務先が横浜である外国人かどちらかだった。しかし戦後になると昔からの地元住人ではなく、鎌倉が好きで移り住んできた者がたくさんいる。わたしは彼らのことをそう呼んでいるのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・戦後、鎌倉が好きな人たちが移り住んできます。
|
|
| 登場人物 |
| 大佛 次郎 |
物語の語り手。小説家。 |
| 野村 光一 |
音楽評論家。 |
|
|
  |