| . |
 |
|
あらすじ
頼朝が家来足軽を含め117万人の武士を引き連れ、富士の裾野で大巻狩りを行なった。それに乗じて曽我兄弟は父の仇・工藤祐経を討とうと計画していた…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・頼朝は多くの御家人を引き連れ富士の裾野での大巻狩りに向かいます。
|
|
| 登場人物 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。 |
| 曽我十郎祐成 |
曽我兄弟の兄。幼名・一萬丸。 |
| 曽我五郎時致 |
曽我兄弟の弟。幼名・箱王丸。 |
| 河津 祐泰 |
曽我兄弟の亡父。 |
| 畠山 重忠 |
頼朝の家来。 |
| 工藤 祐経 |
頼朝の家来。曽我兄弟の仇。 |
| 梶原源太景季 |
頼朝の家来。 |
| 愛甲 六郎 |
頼朝の家来。 |
| 平石右馬之介 |
頼朝の家来。 |
| 岡部 三郎 |
頼朝の家来。 |
| 原 小次郎 |
頼朝の家来。 |
| 御所黒弥吾 |
頼朝の家来。 |
| 加藤弥太郎 |
頼朝の家来。 |
| 船越 八郎 |
頼朝の家来。 |
| 海野小太郎幸氏 |
頼朝の家来。 |
| 伊豆小四郎 |
頼朝の家来。 |
| 臼杵 八郎 |
頼朝の家来。 |
|
| . |
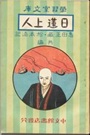 |
|
あらすじ
安房国東条の漁師の子として産まれた善日麿は清澄寺に預けられ修業を積んだ。そして青年僧となった彼は名を「蓮長」と改め、多宗派の研究のため鎌倉へ遊学することになった…。
|
|
| 作品の舞台 |
松葉ヶ谷・・・鎌倉入りした日蓮は庵を結びます。
龍ノ口・・・日蓮は処刑されるために龍ノ口へ送られます。
|
|
| 登場人物 |
| 日蓮 |
安房国東條生まれの高僧。日蓮宗の祖。善日麿→蓮長→日蓮と名を改める。 |
| 貫名 重忠 |
日蓮の父。号は「妙日」。元遠江国貫名の領主だった漁師。 |
| 梅菊 |
日蓮の母。号は「妙蓮」。 |
| 道善坊 |
清澄寺住職。日蓮の師。 |
| 日昭 |
日蓮の弟子。 |
| 日朗 |
日蓮の弟子。 |
| 四条金吾頼基 |
幕府の御家人。日蓮に帰依。 |
| 池上右衛門太夫宗仲 |
武蔵国池上の武士。日蓮に帰依。 |
| 本間 三郎 |
佐渡の地頭。日蓮に帰依。 |
| 遠藤 為盛 |
佐渡の御陵守。日蓮に帰依。 |
| 北条 重時 |
鎌倉幕府連署。 |
| 北条 長時 |
重時の嫡男。鎌倉幕府6代執権。 |
| 北条 時宗 |
鎌倉幕府8代執権。 |
| 工藤 吉高 |
安房国天津城主。 |
| 主人 |
程ヶ谷宿の宿屋の主人。 |
|
| . |
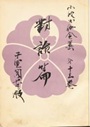 |
|
あらすじ
母が叔母の家に遊びに行ったため、鎌倉の別荘で留守番をすることになった鳥居家の令嬢・林子は下女のお谷から星井家の未亡人・小夜子が泊りがけで遊びに来ることを知らされた。林子は慌てるが、どうやらお谷は横須賀に住む叔父の家から誰か手伝いを寄越してもらえるよう頼んでいたのだ。そして横須賀の家から訪ねてきたのは、世間知らずな音楽史の妻・濱律子だった…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・鳥居家の別荘で林子が留守番をしています。
|
|
| 登場人物 |
| 鳥居 林子 |
鳥居家の令嬢。 |
| 鳥居夫人 |
林子の母。 |
| お谷 |
鳥居家の下女。 |
| 星井小夜子 |
鳥居夫人の友人。未亡人。 |
| 星井子爵 |
小夜子の亡夫。 |
| 叔父 |
横須賀に住む林子の叔父。 |
| 叔母 |
叔父の妻。 |
| 濱 律子 |
叔父の知人。音楽師の妻。派手好きで厚化粧。 |
|
| . |
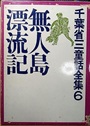 |
|
あらすじ
名馬の里として知られる引田郷には二人の領主がいました。東牧には「馬六大尽」と呼ばれる馬飼六右衛門が、西牧には「鬼兵衛長者」と呼ばれる開田萩兵衛が治めていたが、「馬競」となるとお互い闘争心が燃え上がるが、意地の悪い萩兵衛が姑息な手を使って勝っていた。ある日馬飼が育てる馬の中に、ひと際気性が悪く力強い馬をみつけた少年・陸奥丸は、馬飼の娘・桃枝に見いだされ馬競に参加することになった…。
|
|
| 作品の舞台 |
| 鎌倉・・・引田郷に鎌倉方から駒送りの出張で武士がやってきます。 |
|
| 登場人物 |
| 馬飼六右衛門 |
引田郷東牧の領主。通称「馬六大尽」。 |
| 桃枝 |
六右衛門の娘。勝ち気な少女。 |
| 毛胆の小源太 |
馬飼家の小者頭。 |
| 三吉 |
馬飼家の小者。 |
| 陸奥丸 |
奥州生まれの少年。馬飼家の小者となる。 |
| 開田萩兵衛 |
引田郷西牧の領主。通称「鬼兵衛長者」。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。 |
| 三浦主馬頭清臣 |
鎌倉方の武士。駒送りの出張で引田郷にやってくる。 |
| 千菊丸 |
清臣の子。 |
|
| . |
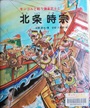 |
| モンゴルと戦う鎌倉武士と 北条時宗 |
著:浜野卓也
絵:吉松八重樹 |
さ・え・ら書房 |
|
あらすじ
幕府の重臣・安達義景邸で産まれた相模太郎時宗は、その後すくすくと成長し浜で行なわれる笠懸でも見事な結果を出す若武者となった。しかしモンゴルからの国書が幕府が送られてきたことで、若い年齢で執権職を任されることになり、元との激しい戦いに臨むことになった…。
|
|
| 作品の舞台 |
極楽寺坂・・・北条重時の館があります。
甘縄・・・時宗が産まれた安達義景の館があります。
建長寺・・・禅宗に帰依する時宗が座禅を組みます。
松葉ヶ谷・・・鎌倉へやってきた日蓮が庵を組みます。
|
|
| 登場人物 |
| 北条 時宗 |
鎌倉幕府8代執権。幼名・正寿丸。相模太郎。 |
| 達姫 |
時宗の妻。泰盛の異母妹。 |
| 幸寿 |
時宗の子。後の北条貞時。 |
| 北条 時頼 |
時宗の父。鎌倉幕府5代執権。最明寺入道。 |
| 葛西殿 |
時宗の母。重時の娘。 |
| 北条 重時 |
時頼の舅。長時・葛西殿の父。極楽寺流北条氏の祖。 |
| 北条 長時 |
重時の嫡男。鎌倉幕府6代執権。 |
| 北条 政村 |
重時の異母弟。鎌倉幕府7代執権。時宗が執権時に連署をつとめる。 |
| 北条 時氏 |
時頼の亡父。28歳で死去。 |
| 松下禅尼 |
時頼の母。 |
| 北条 宗政 |
時宗の弟。 |
| 安達 義景 |
幕府の有力御家人。 |
| 安達 泰盛 |
幕府の有力御家人。義景の三男で嫡男。評定衆。 |
| 安達 盛宗 |
幕府の御家人。泰盛の嫡男。 |
| 平 頼綱 |
幕府の有力御家人。得宗家御内人。 |
| 三浦 泰連 |
幕府の御家人。遠江七郎。 |
| 宗尊親王 |
鎌倉幕府7代将軍。 |
| 少弐 資能 |
鎮西奉行。 |
| 少弐 経資 |
資能の長男。大宰府の将。 |
| 少弐 資時 |
経資の長男。日本軍の総大将。 |
| 少弐 景資 |
資能の三男。経資の弟。対馬の地頭。 |
| 竹崎五郎季長 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国益城郡豊福村の住人。 |
| 小菊 |
季長の妻。 |
| 太郎 |
季長の長男。 |
| しの |
季長の長女。 |
| 弥四郎 |
竹崎家の作人。季長のお気に入り。 |
| 弥三郎 |
弥四郎の亡父。竹崎家の作人。 |
| 三井 資長 |
元寇の日本軍の侍大将。季長の姉婿。 |
| 島津 久経 |
元寇の日本軍の侍大将。薩摩国の住人。 |
| 島津 長久 |
元寇の日本軍の侍大将。薩摩国の住人。久経の弟。 |
| 菊池次郎武房 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国の住人。 |
| 白石六郎通泰 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国の住人。 |
| 託摩 頼経 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国の住人。 |
| 託摩別当太郎頼秀 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国の住人。 |
| 朝倉八郎吉直 |
元寇の日本軍の侍大将。肥後国の住人。 |
| 河野六郎通有 |
元寇の日本軍の侍大将。伊予国の住人。 |
| 河野八郎通忠 |
元寇の日本軍の侍大将。伊予国の住人。通有の嫡男。 |
| 河野伯耆守通時 |
元寇の日本軍の侍大将。伊予国の住人。通有のおじ。 |
| 大友 貞親 |
元寇の日本軍の侍大将。豊後国の住人。豊後守護。 |
| 竜造寺季時 |
元寇の日本軍の侍大将。肥前国の住人。 |
| 竜造寺季友 |
元寇の日本軍の侍大将。肥前国の住人。季時の弟。 |
| 平 景隆 |
壱岐守護代。 |
| 宋 助国 |
対馬守護代。 |
| 右馬次郎 |
助国の息子。 |
| 小次郎 |
助国の家来。 |
| 兵衛次郎 |
助国の家来。 |
| 直継 |
助国の家来。 |
| 塔二郎 |
対馬の漁民。 |
| 弥二郎 |
対馬の漁民。 |
| 佐志次郎 |
松浦党の勇将。 |
| 草野次郎 |
松浦党の勇将。 |
| 法印隆弁 |
鶴岡八幡宮の僧。 |
| 蘭渓道隆 |
建長寺の僧。 |
| 無学祖元 |
南宋の禅僧。道隆の弟子。 |
| 日蓮 |
日蓮宗の祖。幼名・薬王丸。 |
| 東条 景信 |
安房国小湊の地頭。日蓮の帰依者。 |
| ジンギス・カン |
モンゴル帝国初代皇帝。 |
| フビライ・ハン |
モンゴル帝国5代皇帝。 |
| 趙 良弼 |
モンゴルの重鎮外交官。 |
| 杜 正忠 |
モンゴルの使者。 |
| 何 文著 |
モンゴルの使者。中国人。 |
|
| . |
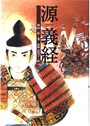 |
|
あらすじ
雪が降る京の清水寺に3人の子供の助命を願う一人の若い母親の姿があった。母の名は常磐。平治の乱で敗れた源氏の嫡流である7歳の今若、5歳の乙若、1歳の牛若はいつしか追われる身となっていたのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・1180年、頼朝は父の居館があった鎌倉に自らの本拠地を置きます。
鶴岡八幡宮・・・1181年、若宮宝殿の棟上げ式が行なわれます。
腰越・・・1185年、義経は大江広元に腰越状を渡します。
|