| . |
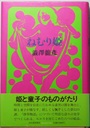 |
|
あらすじ
下谷に住む働き者の大工・音吉が葛西の寺の門の細工を見てくると出て行ってから突然姿を消してしまった。そして1か月半ほど経ったある日、音吉と同じ長屋に住む者が江ノ島へ遊びに行くと音吉の姿を見かけたというのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
腰越・・・木地屋の女元締・きらら姫の縄張りです。
大町・・・日蓮が辻説法をします。
|
|
| 登場人物 |
| 音吉 |
下谷・広徳寺前の長屋に住む貧乏大工の息子。18歳。働き者の若い大工。 |
| きらら姫 |
鎌倉・腰越のお猿畠を本拠とする木地屋の女元締。 |
| 能登坊丹空 |
きらら姫の片腕。 |
| 願人坊主 |
鈴を鳴らしながら街を歩く坊主。 |
| 男 |
音吉と同じ長屋に住む男。 |
| 日蓮 |
僧。日蓮宗の祖。 |
| 日昭 |
日蓮の弟子。40歳。 |
| 日朗 |
日蓮の弟子。15歳。吉祥丸。 |
| 日興 |
日蓮の弟子。14歳。伯耆公。 |
| 四条金吾頼基 |
日蓮の弟子。幕府の御家人。 |
| 荏原左衛門尉義宗 |
日蓮の弟子。幕府の御家人。 |
| 池上 宗仲 |
日蓮の弟子。幕府の御家人。 |
| 進士太郎善春 |
日蓮の弟子。幕府の御家人。 |
| 工藤 吉隆 |
日蓮の弟子。幕府の御家人。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
滑川の河口の近くに長い間ほったらかしとなっている木造の大きな船があった。この船は幕府の3代将軍・源実朝が宋の工人・陳和卿に作らせた船だった。船の中には繍帳に描かれている豊満な美人が退屈そうにしていた。そこへ1羽の鸚鵡が飛んできて美人に話しかけた…。
|
|
| 作品の舞台 |
由比ガ浜・・・砂浜に大きな船がほったらかしになっていました。
弁ガ谷・・・陳和卿が住む草庵があります。
|
|
| 登場人物 |
| 美人 |
大きな船に掛けられている繍帳に描かれている豊満な美人。 |
| 鸚鵡 |
船に飛んできたオウム。 |
| 俊乗坊重源 |
醍醐寺の高僧。 |
| 空諦 |
俊乗坊の弟子。 |
| 源 実朝 |
鎌倉幕府3代将軍。右大臣。 |
| 陳和卿 |
宋の工人。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
商家の子弟たちの集まりで、少々発育不全の気がある彦七は他の者から「文覚上人のように華蔵院の十王院にある十王像をもってこい」とからかわれたのだが、彼はまじめに御堂へ行き十王像ではなく護法童子像を持ってきてしまった。他の者たちは驚いていたが、彼は帰りに像を御堂へ戻して家に戻った。翌日彦七が自宅にいると護法の化身が彼を訪ねてきた…。
|
|
| 作品の舞台 |
浄光明寺・・・塔頭の華蔵院から彦七が護法童子像を持ち出してしまいます。
長谷・・・商家の子弟たちが集まって芸者をあげてどんちゃん騒ぎをします。
建長寺・・・寺の近くに彦七の実家があります。
鶴岡八幡宮・・・二の鳥居の近くに宿屋「桔梗屋」があります。 |
|
| 登場人物 |
| 彦七 |
建長寺近くにある商家の息子。23歳。生まれつきの発育不全。 |
| お駒 |
彦七の女房。26歳。 |
| お紺 |
宿屋「桔梗屋」の娘。 |
| 乙天 |
浄光明寺塔頭・華蔵院にある護法童子像の化身。 |
| 石川六兵衛 |
江戸日本橋の分限者。江戸追放になり鎌倉へ移住。彦七の祖先。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
当代きっての詩人・「高蘭亭」こと高野蘭亭には一つ困ったことがあった。それは酒を飲むと口が悪くなり、さらに自分が集めている盃の自慢話を長々とすることだった。ある日、彼の女弟子・栄女に『信長記』を読ませていたところ、そこに書かれていた「髑髏盃」をどうしても手に入れたくなった。そして彼は友人の秋山玉山とその弟子と共に極楽寺にある十一人塚へ行って墓を荒らして盃を奪おうと企てた…。
|
|
| 作品の舞台 |
円覚寺・・・寺近くの瑞鹿山の下にある草堂が高野蘭亭の住まいです。
教恩寺・・・蘭亭が持つ黒盃は寺の寺宝でした。
極楽寺・・・ある夜、蘭亭は十一人塚を荒らそうとします。
|
|
| 登場人物 |
| 高野 蘭亭 |
当代きっての詩人・俳人・書家。49歳。17歳から盲目。酒癖が悪く盗癖がある。号は「高蘭亭」。 |
| 秋山 玉山 |
蘭亭の友人。49歳。蘭亭と並ぶ当代きっての詩人。号は「秋玉山」。 |
| 栄女 |
蘭亭の女弟子。30過ぎ。 |
| 父 |
蘭亭の亡父。江戸日本橋・小田原町にある魚問屋の主人。俳人。号は「百里居士」。 |
| 若もの |
玉山の若い弟子。 |
| 小座頭 |
蘭亭の実家で居候していた蘭亭と同じ年位の座頭。 |
| 天狗 |
妖怪。 |
|
|
  |