| . |
 |
|
あらすじ
本所相生町の大工の女房・てるが東慶寺に駆け込んできた。しかし、東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎は、てるの生まれが「武州多摩郡小山村」だということが気になった。そこで和三郎がてるの住む本所の長屋へ行ってみると、そんな夫婦は住んでいないということがわかる・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・和三郎が住む餅菓子屋は、駆込寺(東慶寺)の門前にあります。
鎌倉・・・佐田家の知行地は鎌倉でした。
|
|
| 登場人物 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋。寺の御用宿。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋。寺の御用宿。 |
| 徹秀法悟尼 |
塔頭「蔭涼軒」軒主。寺の院代。 |
| 金八 |
寺の御用飛脚。 |
| 文吉 |
寺の御用飛脚。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。 |
| 佐田彦九郎 |
下谷御徒町の旗本。 |
| 藤代勘左衛門 |
佐田家の御用人。 |
| 鉄平 |
佐田家の中間。 |
| あき |
佐田家の奉公人。 |
| 柳沢 吉保 |
5代将軍・綱吉の側用人。 |
| 柳沢 吉里 |
吉保の息子。 |
| 伊東仙右衛門 |
柳沢家の徒目付。 |
| 近 |
仙右衛門の妻。 |
| 弥之吉 |
本所相生町の大工。 |
| てる |
弥之吉の妻。 |
| 八五郎 |
弥之吉の弟分。 |
|
| . |
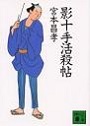 |
|
あらすじ
夫と離縁をしたいがため、れんが東慶寺に駆け込んできた。そこでれんの素性を調べていくと、れんの夫・良吉は既に死んでいることがわかった。寺役人の野村市助は、その点をれんに尋ねてみると・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 沢田 |
喜連川家のお付役人。 |
| 丸屋七兵衛 |
駿河国府中伝馬町の呉服商。 |
| よし |
七兵衛の妻。 |
| 幸吉 |
七兵衛の倅。父の死後「七兵衛」の名を継ぐ。 |
| れん |
幸吉の妻。 |
| くま |
幸吉の実母。 |
| 吉井内蔵允 |
れんの父。土岐家で若君傳役をつとめる。 |
| 伍助 |
吉井家の下僕。 |
| 土岐兵庫頼泰 |
土岐家当主。 |
| 志村金五郎 |
土岐家御家人。 |
| 茂兵衛 |
志村家の下僕。 |
| 太一 |
茂兵衛の孫。熊の膏薬売り。 |
| 黒田怱左衛門 |
信濃飯山藩牢人。 |
| 牧野因幡守 |
寺社奉行。 |
| 桑山仙右衛門 |
白髪の老武士。 |
| 加藤三之介 |
仙右衛門の甥。 |
|
| . |
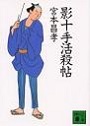 |
|
あらすじ
和三郎が明月院に餅菓子を届けに向かう途中、子連れの女・なをに出会った。なをは酒乱の夫・又吉と離縁をするために富山から出てきたのだという。それまで優しかった又吉だったが、4年前から急に人が変わってしまったかのようになったというのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
明月院・・・和三郎は、お得意先の明月院に餅菓子を運ぶ途中、なをと出会います。 |
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 沢田 |
喜連川家のお付役人。 |
| 五郎左衛門 |
富山薬「反魂丹」売りの帳主。 |
| ろく |
五郎左衛門の妻。 |
| 長次 |
五郎左衛門の手下。 |
| 儀助 |
元「反魂丹」売りの帳主。 |
| 又吉 |
「反魂丹」売り。 |
| なを |
又吉の妻。 |
| よし |
又吉となをの娘。 |
| 岩蔵 |
「反魂丹」売り。 |
| 前田 正甫 |
富山藩2代藩主。 |
| 秋田 輝季 |
陸奥国三春藩主。 |
| 万代 常閑 |
備前岡山の医師。 |
| せん |
千住の宿「日光屋」の女中。 |
|
| . |
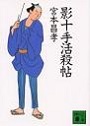 |
|
あらすじ
江戸の深川に住むみつは夫・善蔵との離縁のため、東慶寺に駆け込んできた。みつの付き添いで来ていた長屋の大家・伊兵衛夫妻は、善蔵夫妻のことを褒めちぎりみつに思い直すよう懸命に説得している。すると、みつは思わぬことを言いだした・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 沢田 |
喜連川家のお付役人。 |
| 善蔵 |
江戸深川北松代町忠五郎店の店子。 |
| みつ |
善蔵の妻。 |
| 伊兵衛 |
忠五郎店の大家。 |
| むめ |
伊兵衛の妻。 |
| 古田綱之助 |
備前岡山藩小姓組八十石の武士。 |
| 波津 |
綱之助の妻。 |
| 古田源太夫 |
綱之助の父。 |
| 芙佐 |
綱之助の母。 |
| 小野伝七郎 |
波津の兄。 |
| 多田 数馬 |
古田家の若党。 |
| 弥次郎 |
古田家の中間。 |
| 遍斎 |
一人暮らしの易者。 |
|
| . |
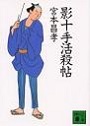 |
|
あらすじ
東慶寺にかんという女が駆け込んできた。しかし、かんは離縁を望んでいるわけではなく百姓をしている夫・留七の心を入れ替えさせたい一心で来たようだった。その内情を調べるため和三郎は、御庭番の娘・紀乃とともにかん夫婦が住む川崎宿へ向かったが、そこで二人は斬殺されている留七を発見する・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 沢田 |
喜連川家のお付役人。 |
| 高田郡兵衛 |
赤穂藩浪人。 |
| 毛利小平太 |
赤穂藩浪人。 |
| 小山田庄左衛門 |
赤穂藩浪人。 |
| 中村清右衛門 |
赤穂藩浪人。 |
| 鈴田 重八 |
赤穂藩浪人。 |
| 高田弥五兵衛 |
郡兵衛の兄。 |
| 内田三郎右衛門 |
郡兵衛の伯父。 |
| 志緒 |
郡兵衛の妻。 |
| 酬山 |
高輪泉岳寺住職。 |
| 留七 |
江戸金杉村の百姓。 |
| かん |
留七の妻。 |
| 八五郎 |
大山帰りの酔っぱらい。 |
| 渡辺主膳正 |
旗本。 |
| 理江 |
渡辺の後妻。 |
| 牧田与三郎 |
渡辺家御家人。 |
| 和泉屋竹翁 |
照降町の菓子舗「和泉屋」主人。 |
| ます |
和泉屋の妻。 |
| 大岡越前守忠相 |
南町奉行。 |
|
| . |
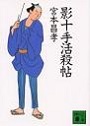 |
|
あらすじ
東慶寺につねという女が駆け込んできた。つねは夫・菊之丞と6年連れ添っても一向に夫婦関係がないことに悩み駆け込んできたようだ。つねの実家である呉服商の小丸屋は、娘に本家の次男・菊之丞を婿に取り、商売も怠りはない様子なのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 沢田 |
喜連川家のお付役人。 |
| 小丸屋利八 |
神田金沢町の呉服商「小丸屋」の主人。 |
| とき |
利八の妻。 |
| つね |
利八の娘。 |
| 小丸屋加右衛門 |
京都にある「小丸屋」本店の主人。 |
| たみ江 |
加右衛門の妻。 |
| 万太郎 |
加右衛門の長男。 |
| 菊之丞 |
加右衛門の次男。 |
| 福 |
つねの幼なじみ。 |
| 治兵衛 |
大坂今橋通境筋の紙問屋主人。 |
| くま |
治兵衛の妻。 |
| 於兎蔵 |
治兵衛の甥。 |
| 小春 |
女郎。 |
| 吉次 |
大坂道頓堀の貝塚屋仁三郎お抱えの色子。 |
| 今宮の忘八 |
ごろつき。 |
| 三之輪の権七 |
ごろつき。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
芝居好きで金遣いの荒い長吉に、愛想を尽かした女房のさとが東慶寺に駆け込んできた。早速和三郎は長吉のことを探りに浅草へ向かったが、そこで長吉の死体を発見する。紀乃の話によると、「助六小僧」と呼ばれていた盗人の正体が長吉だったというのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 金八 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 恵比須屋長吉 |
浅草田原町2丁目の小間物商。芝居好き。 |
| さと |
長吉の女房。 |
| 祥(さち) |
松島町の旗本・美濃部家の息女。紀乃の親友。 |
| れん |
駿河国府中伝馬町の呉服商「丸屋」の女房。 |
| 沢辺九郎左衛門 |
戸塚宿で本陣をつとめる名主。 |
| 捨次 |
芝居小屋の下男。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
何度となく東慶寺に駆け込むことを繰り返す浅草の銘酒商の跡取り息子の女房・しまのことを、寺役人の市助たちは「おねだり女房」と呼んでいた。江戸の豪商の娘として甘やかされて育てられたため、しまは大した理由もなく鎌倉を訪ねるのだ。しかし晩秋のある日の晩、しまの亭主・長太郎が「しまの姿が見えなくなった」と東慶寺を訪ねてきた・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 徹秀法悟尼 |
東慶寺塔頭蔭涼軒主。東慶寺代理住職。 |
| 播磨屋弥惣次 |
江戸浅草並木町の銘酒商。 |
| きん |
弥惣次の女房。 |
| 長太郎 |
弥惣次の跡取り息子。 |
| しま |
長太郎の女房。 |
| 卯平 |
弥惣次の父。鋳掛屋。 |
| 奈良屋七郎右衛門 |
江戸屈指の材木商。通称「奈良七」。しまの父親。 |
| 奈良屋政五郎 |
材木商。元・奈良七の大番頭。 |
| 藤 |
きんの寺子屋に通う娘。 |
| 田所重左衛門 |
浪人。元・掛川藩士。 |
| 充江 |
重左衛門の女房。 |
| 佐知 |
重左衛門の娘。 |
| 直助 |
重左衛門の下僕。 |
| 田所伊十郎 |
重左衛門の弟。 |
| 和泉屋竹翁 |
日本橋照降町の菓子商。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
容姿が不細工で年増の下女・とよは、向島の長命寺へ水を汲みに行った帰り道、二人組のごろつきに襲われた。しかしそこへとよが一方的に恋焦がれていた板前の浅吉が助けに入り、彼女は難を逃れることができた。やがてとよは浅吉と夫婦になったのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| とよ |
浅草駒形町の料理茶屋「富川」の通いの下女。 |
| 浅吉 |
堺町の料理茶屋「才牛」の板前。元「富川」の板前。 |
| 岩松 |
とよの父。屋根葺き職人。2年前に死亡。 |
| 加兵衛 |
屋根葺き職人の棟梁。 |
| 治三郎 |
「富川」の亭主。 |
| 清六 |
とよの新しい亭主。 |
| 慈念 |
向島の長命寺の僧。 |
| 伝蔵 |
武士の中間。小男。 |
| 力士鉄 |
武士の中間。大男。 |
| 白子屋庄三郎 |
江戸新材木町の材木商。 |
| つね |
庄三郎の妻。 |
| 熊 |
庄三郎の娘。美人でわがまま。 |
| 忠八 |
白子屋の番頭。 |
| 加賀屋長兵衛 |
江戸新材木町の材木商。 |
| 又四郎 |
元・大伝馬町の地主の番頭。 |
| きく |
白子屋の下女。 |
| 笠間の七郎次 |
凶状持ち。 |
| 駒 |
藤沢の待合茶屋「白帆屋」の跡取りの嫁。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
江戸松島町の村垣家に駆け込んできた農夫の女房・よねを鎌倉の東慶寺へ連れて行くことになった紀乃。しかし、鎌倉に入る手前にある「離れ山」に差し掛かった頃、紀乃は謎の牢人たちに襲われ連れ去られてしまう。どうやらよねも牢人の仲間だったようで・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・東慶寺門前の餅菓子屋の倅・和三郎と、東慶寺寺役人の野村市助が活躍します。
|
|
| 登場人物 |
| 野村 市助 |
東慶寺の寺役人。尼僧から「焼き芋」というあだ名で呼ばれている。 |
| 餅菓子屋平左衛門 |
東慶寺門前の餅菓子屋「餅平」の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 和三郎 |
平左衛門の倅。忍びの裔で市助とともに東慶寺を守護する。 |
| きね |
平左衛門の妻。 |
| 煎餅屋長右衛門 |
東慶寺門前の煎餅屋の主人。東慶寺の御用宿。 |
| 村垣 吉平 |
公儀御庭番。 |
| 村垣 紀乃 |
吉平の娘。東慶寺に奉公し、市助や和三郎の手助けをする。 |
| 村垣 十和 |
吉平の妻。病死。 |
| 簗田 彦助 |
吉平の家来。 |
| 植村 平七 |
吉平の家来。 |
| 文吉 |
東慶寺御用飛脚。 |
| 長田三右衛門 |
幕府の目付。 |
| 戸田右近将監 |
江戸城御廊下番。 |
| 幸江 |
三右衛門の妻。 |
| 水野 忠恒 |
信濃国松本藩主。 |
| 水野 忠穀 |
忠恒の叔父。 |
| 毛利 師就 |
長門国長府毛利家の世子。 |
| 利兵衛 |
松本城下宮村町の大工。 |
| 阿む |
利兵衛の娘。 |
| 養之助 |
三右衛門の家来。 |
| 信次郎 |
三右衛門の家来。 |
| 七内 |
三右衛門の家来。 |
| 小膳 |
三右衛門の家来。 |
| 本亀の龍 |
牢人。本名は「龍四郎」。 |
| 酒井 頼母 |
小十人組。450石。龍四郎の兄。 |
| 青柳 |
手附(代官の補佐役)。 |
| 桶川 郡蔵 |
小普請組。 |
| 宮地 三弥 |
小普請組。 |
| 千瀬 |
三弥の妻。 |
| 寅次 |
桶川家の奉公人。 |
| 菅井六兵衛 |
牢人。元・松本藩士。 |
| 江木万之助 |
牢人。元・松本藩士。 |
| 内藤 一学 |
牢人。元・松本藩士。 |
| 権助 |
小悪党。 |
| 久 |
小悪党。 |
| 五左衛門 |
信濃筑摩郡の長百姓。 |
| 孫一 |
五左衛門の倅。 |
| 小助 |
下総の農夫。 |
| よね |
小助の女房。 |
| やす |
多摩川支流の乞田川沿いの農家の後家。 |
|
|
  |