| . |
 |
|
あらすじ
10歳で備中・宝福寺に預けられた雪舟は、絵の才能があることを見いだされ、京の相国寺へ絵の勉強に行くこととなった。相国寺には幕府の御用絵師の僧・周文に仕え、多くの弟子と共に絵を学ぶのだが…。
|
|
| 作品の舞台 |
建長寺・・・雪舟は玉隠禅師を訪ねます。
|
|
| 登場人物 |
| 雪舟 |
備中国三須村赤浜生まれの禅僧・画僧。 |
| 秋月 |
雪舟の弟子。薩摩生まれの画僧。 |
| 春林 |
京・相国寺の高僧。相国寺第36世住持。雪舟の仏教の師。 |
| 周文 |
京・相国寺の禅僧・画僧。幕府の御用絵師。宗元画の大家。雪舟の絵の師。 |
| 小栗 宗湛 |
京・相国寺の禅僧・画僧。雪舟の2歳年上。周文没後の御用絵師。周文の弟子。 |
| 万里集九 |
元・相国寺の僧。美濃国正法寺の住職。 |
| 友雲 |
元・相国寺の僧。遠江国清見寺の住職。 |
| 玉峰 |
元・相国寺の僧。羽前国崇禅寺の住職。 |
| 桂菴 |
雪舟と明へ渡航した禅僧。薩摩生まれ。 |
| 村菴 |
京・衣笠山の庵に住む老僧。 |
| 蔗菴 |
京・東福寺の高僧。東福寺第174世住持。 |
| 宝福寺住職 |
備中国宝福寺の住職。幼い雪舟を預かり絵の才能を見出す。 |
| 玉隠 |
相模国鎌倉・建長寺の高僧。建長寺第164世住持。 |
| 祥啓 |
建長寺塔頭宝珠院の書記。啓書記。後に宗元画の大家。 |
| 足利 義政 |
室町幕府8代将軍。 |
| 飯尾肥前守 |
幕府の役人。宗湛の後ろ盾。 |
| 狩野 正信 |
幕府の御用絵師。狩野派の祖。 |
| 大内 政弘 |
大内家14代当主。周防守護。雪舟を庇護。 |
| 大内 教弘 |
政弘の亡父。大内家13代当主。 |
| 大内 義興 |
政弘の嫡男。大内家15代当主。 |
| 大友 親繁 |
大友家15代当主。豊後守護。 |
| 大友 政親 |
愛重の嫡男。大友家16代当主。 |
| 姚大臣 |
北京の役人。 |
| 張有声 |
明国の著名な絵師。 |
| 李在 |
明国の著名な絵師。 |
|
| . |
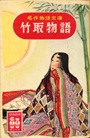 |
|
あらすじ
1261年、幕府に捕らえられた日蓮は伊豆へ島流しされることになった。そして伊豆へ送られる途中、役人たちは地続きであるとだまして岩の上に日蓮を下ろし帰ってしまいました。岩の上に立った日蓮は突然大声でお経を唱え始めると目の前に一艘の船が現れました…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・日蓮を島流しにした後、極楽寺入道や息子の長時が熱病にかかります。
|
|
| 登場人物 |
| 日蓮 |
安房国生まれの僧。日蓮宗の祖。 |
| 弥三郎 |
伊豆国川奈の漁師。日蓮に帰依。 |
| 妻 |
弥三郎の妻。 |
| 伊東 頼高 |
伊豆国伊東の御家人。日蓮に帰依。 |
| 北条 重時 |
鎌倉幕府連署。極楽寺入道。 |
| 北条 長時 |
重時の子。鎌倉幕府6代執権。 |
|
| . |
 |
偉人達もしくじりまくり!?
日本史しくじり大図鑑 |
ライター:深谷美和
イラスト:中川いさみ |
ホビージャパン |
|
あらすじ
日本の偉人たちは大きな成功を成し遂げたことによって名を残しているが、多くの失敗も経験している。彼らはその失敗で何を学んで成功に結び付けたかを辿っていく…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・頼朝が幕府を開きます。
|