| . |
 |
|
あらすじ
孤児となった俊恵は、昌平寺の高僧・慧仙に引き取られ修行僧となった。その後円覚寺、建仁寺で修行を積み24歳になって再び昌平寺に戻ってきた。そんな彼がある日を境に「真如をさがす」と大声で喚き散らし奇行を見せるようになってしまった・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
円覚寺・・・俊恵が修業をしに行きます。
|
|
| 登場人物 |
| 俊恵 |
武蔵国・昌平寺の僧。 |
| 慧仙 |
昌平寺の高僧。俊恵の師。 |
| 明真 |
昌平寺の小坊主。 |
| 七兵衛 |
昌平寺の墓守。 |
| 弥助 |
七兵衛の息子。 |
| 花世 |
弥助の娘。七兵衛の孫娘。 |
| 閑右衛門 |
村の庄屋の隠居。 |
| 老人 |
昌平寺の檀家。 |
| 農夫 |
寺の近くに住む農夫。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
名探偵・神津恭介が盲腸炎で東大病院の外科病棟に入院した。見舞いに行った松下研三は病床の神津から退屈しのぎの話題を求められ、「『源義経=成吉思汗』説」を提案した。天才探偵はその話題に刺激され、大胆な推理をめぐらせていく・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
材木座・・・神津がジンギスカンの謎を追う話の中で、材木座の名前の由来が紹介されます。
|
|
| 登場人物 |
| 神津 恭介 |
天才探偵。東大医学部法医学教室助教授。 |
| 松下 研三 |
探偵作家。 |
| 松下 滋子 |
研三の妻。 |
| 井村 梅吉 |
東大文学部歴史学教室助教授。神津の友人。 |
| 大麻 鎮子 |
井村の助手。 |
| 志村 義行 |
神津の遠縁。貿易商。 |
| 志村 悦子 |
義行の娘。 |
| 渡辺 勝 |
海軍史研究家。神津の友人。 |
| 柳原 緑風 |
元・報知新聞記者。 |
| 斎藤 信彦 |
元・新聞記者。 |
| 仁科 東子 |
神津の講演を聴講した女性。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
小野寺十内は播州赤穂・浅野家京都留守居役で家中一の学者だった。ある日、浅野家の若侍が花見の遊興に際して悪ふざけをしようとしたところ、それを威勢のいい女にたしなめられる事件があった…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・間宮と川崎が遠乗りに向かいます。
|
|
| 登場人物 |
| 小野寺十内 |
播州赤穂・浅野家の京都留守居役。150石。家中一の学者。 |
| 丹女 |
十内の妻。主馬の娘。 |
| 小野寺幸右衛門 |
十内の息子。浅野藩士。 |
| 溝口 内記 |
奥州磐城郡横田の旗本。 |
| 古川 主馬 |
内記の家来。丹女の父。 |
| 浅野内匠頭 |
播州赤穂・浅野家当主。 |
| 吉田忠左衛門 |
赤穂藩士。 |
| 原惣右衛門 |
赤穂藩士。 |
| 堀部安兵衛 |
赤穂藩士。 |
| 間宮定之進 |
浅野家の近習。若侍。 |
| 川崎 周蔵 |
浅野家の近習。若侍。 |
| 植村藤右衛門 |
浅野家の馬役。 |
| 重五郎 |
浅野家の馬丁頭。 |
| 茂助 |
浅野家の馬丁。 |
| 伊藤 仁斎 |
京都堀川に住む十内の筆の師。 |
| 藤堂 |
江戸・下谷に住む旗本。 |
| 熊 |
江戸の職人。 |
|
| . |
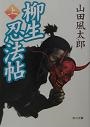 |
|
あらすじ
会津藩の暴君・加藤明成を見限った国家老・堀主水らは明成の配下の会津七本槍衆につかまり、会津藩江戸屋敷へ連れて行かれることとなった。しかしその途中、鎌倉の尼寺・東慶寺に立ち寄り、七本槍衆はそこに匿われていた堀一族の女たちを彼らの目の前で次々と惨殺した。さらに主水たちまでも惨殺され、東慶寺で生き残った主水の娘・千絵ら7人は会津七本槍衆に復讐を誓った。東慶寺住持の義母・天樹院と東海寺の沢庵は、そんな武芸の覚えすらない彼女たちを不憫に思い、彼女たちに紹介した師範役が柳生十兵衛だった・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・会津七本槍衆は、捕縛した堀主水たちを東慶寺に連れて行き、寺に匿われていた堀一族の女たちを惨殺します。
|
|
| 登場人物 |
| 柳生十兵衛三厳 |
将軍家指南番につかず放浪の身の剣豪。愛用刀は「三池典太」。 |
| 加藤左馬助嘉明 |
「賤ヶ岳の七本槍」の一人として名を馳せた戦国大名。11年前に死亡。 |
| 加藤式部少輔明成 |
会津40万石を継ぐ嘉明の子。父とは異なり暴君。 |
| 芦名 銅伯 |
会津七本槍衆(明成の親衛隊)の総首領。107歳。 |
| おゆら |
銅伯の娘。明成の愛妾。27歳。 |
| 鷲ノ巣廉助 |
会津七本槍衆の一人。鉄鋲が得意。 |
| 司馬一眼房 |
会津七本槍衆の一人。鞭使いが得意。 |
| 大道寺鉄斎 |
会津七本槍衆の一人。鎖鎌が得意。 |
| 香炉銀四郎 |
会津七本槍衆の一人。網で惑わすのが得意。 |
| 平賀孫兵衛 |
会津七本槍衆の一人。槍が得意。 |
| 漆戸虹七郎 |
会津七本槍衆の一人。剣が得意。 |
| 具足丈之進 |
会津七本槍衆の一人。狂犬使いが得意。 |
| 天丸 |
丈之進が操る秋田犬。 |
| 地丸 |
丈之進が操る秋田犬。 |
| 風丸 |
丈之進が操る秋田犬。 |
| 堀川嘉兵衛 |
加藤家江戸家老。 |
| 堀主水綱房 |
元・加藤家国家老。 |
| 千絵 |
主水の娘。19歳。 |
| お笛 |
千絵の婢。少し知恵おくれ。18歳。 |
| 多賀井又八郎 |
主水の弟。 |
| 沙和 |
又八郎の妻。30歳。 |
| 真鍋小兵衛 |
主水の弟。 |
| さくら |
小兵衛の娘。17歳。 |
| 稲葉十三郎 |
堀家の家臣。 |
| お圭 |
十三郎の妻。25歳。 |
| 金丸 半作 |
堀家の家臣。 |
| お品 |
半作の妻。27歳。 |
| 板倉 不伝 |
堀家の家臣。 |
| お鳥 |
不伝の娘。20歳。 |
| 天野久太夫 |
堀家の家臣。 |
| 小城 修理 |
堀家の家臣。 |
| 千田 直人 |
堀家の家臣。 |
| 天秀法泰尼 |
東慶寺住持。 |
| 天 樹 院 |
天秀尼の義母。元豊臣秀頼の妻「千姫」。 |
| 国松 |
天秀尼の兄。六条河原で斬首。 |
| 吉田 修理 |
天樹院付きの家老。 |
| 沢庵 |
江戸品川の東海寺の住持。71歳。 |
| 多聞坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 普明坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 雲林坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 薬師坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 竜王坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 十乗坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 嘯竹坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 心華坊 |
沢庵門下の僧。 |
| 庄司甚右衛門 |
傾成屋「西田屋」主人。吉原の開祖。 |
| お糸 |
日本橋の呉服屋「よろず屋」の娘。 |
| 信三郎 |
お糸の婿。京橋八官町の酒屋の息子。 |
| 高砂屋彦右衛門 |
武州粕壁の本陣「高砂屋」の主人。 |
| 紙屋五郎右衛門 |
武州粕壁の本陣「紙屋」の主人。 |
| おとね |
「紙屋」の娘。 |
| 間宮 大学 |
江戸麹町に住む「御小納戸衆」。 |
| 間宮 主馬 |
大学の子。 |
| 田鶴 |
大学の妻。 |
| 大角与右衛門 |
「芦名衆」の一人。 |
| 野呂 万八 |
「芦名衆」の一人。 |
| 柳生但馬守宗矩 |
十兵衛の父。将軍家指南番。剣聖。 |
| 柳生 宗冬 |
十兵衛の弟。将軍家指南番を継ぐ。 |
| 木村助九郎 |
「柳門十哲」の一人。剣人。 |
| 出淵平兵衛 |
「柳門十哲」の一人。剣人。 |
| 庄田喜左衛門 |
「柳門十哲」の一人。剣人。 |
| 村田 与三 |
「柳門十哲」の一人。剣人。 |
| 狭川新左衛門 |
「柳門十哲」の一人。剣人。 |
| 徳川 家光 |
江戸幕府3代将軍。 |
| 徳川 忠長 |
家光の弟。駿河大納言。9年前に切腹。 |
| 保科肥後守正之 |
家光・忠長の異母弟。 |
| 松平伊豆守信綱 |
老中。 |
| 三沢 玄洞 |
江戸城の奥医者。 |
| 三沢 玄達 |
玄洞の弟。医者。 |
| 鳥山 検校 |
当道座の高官。 |
| お園 |
鳥山の娘。 |
| 南光坊天海 |
東叡山寛永寺の開基。家康のブレーンだった政僧。 |
|
| . |
 |
| お忘れですか?モンゴルに渡った義経です |
高木彬光 |
角川文庫 |
|
あらすじ
作家・高木彬光は、鎌倉市腰越にある自邸に九郎判官義経こと成吉思汗が訪ねてきた夢を見た。彬光は過去に『成吉思汗の秘密』という作品で「義経=成吉思汗説」を証明した。あれから20年、夢とは言え彬光は本人と初めて顔を合わせたのだ…。
|
|
| 作品の舞台 |
腰越・・・高木彬光邸に成吉思汗が訪ねてきます。
|
|
| 登場人物 |
| 高木 彬光 |
鎌倉市腰越に住む大作家。 |
| 成吉思汗 |
モンゴル皇帝。その正体は「源 義経」。 |
| 神津 恭介 |
彬光が創作した名探偵。 |
| 松下 研三 |
恭介のワトソン役。雑誌記者。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。義経の異母兄。 |
| 日蓮 |
名僧。日蓮宗の祖。 |
| 梶原 景時 |
幕府御家人。頼朝の懐刀。 |
| 平 清盛 |
平家の棟梁。 |
| 建礼門院徳子 |
清盛の長女。安徳の国母。 |
| 安徳天皇 |
第81代天皇。徳子の子。 |
| 静御前 |
義経の愛妾。白拍子。 |
| 藤原 秀衡 |
奥州藤原氏3代当主。義経の後ろ盾。 |
| 藤原 泰衡 |
秀衡の嫡男。 |
| 愛新覚羅溥儀 |
清朝最後の皇帝。 |
| 愛新覚羅溥傑 |
溥儀の弟。 |
| 愛新覚羅慧生 |
溥傑の長女。 |
| 大久保武道 |
慧生の恋人。 |
| 豊田 有恒 |
作家。 |
| 仁科 東子 |
作家。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
駆込寺として知られる東慶寺の住持は、純真無垢な高辻中納言家の姫・玉渕尼。そんな傷つきやすい彼女を警護し、醜い争いの後始末をつけるのは、彼女の許婚だった”麿”となのる若侍だった。実は彼は朝廷の隠密を務める公卿の子息で、尼君のため地位を捨て、用心棒を務めているのだ・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
東慶寺・・・玉渕尼が住持をつとめています。
由比ガ浜・・・おくにが小舟で流れ着いたのは、由比ガ浜の沖です。 |
|
| 登場人物 |
| 玉 渕 尼 |
東慶寺の住持。高辻中納言家の姫で喜連川家の養女。 |
| 麿 |
「御所忍び」(朝廷の隠密方)を務める公卿の子息。元・12歳年上の玉渕尼の許婚。陰ながら玉渕尼を助ける。 |
| 徹 秀 尼 |
東慶寺の院代の最長老。 |
| 八 兵 衛 |
東慶寺門前の煎餅屋の亭主。実は木曽谷の忍び。駿足の持主。 |
| お か つ |
八兵衛の女房。木曽谷の忍び。遠聴が達者。 |
| 二階堂貞慶 |
喜連川家から派遣された東慶寺の差配。 |
| 三国屋卯兵衛 |
廻船問屋「三国屋」主人。 |
| 三国屋卯太郎 |
卯兵衛の長男。 |
| 三国屋卯之助 |
卯兵衛の次男。 |
| お う め |
卯之助の女房。 |
| お む ら |
うめの母。岡場所の針子。 |
| 与 作 |
上総国のある村の庄屋。5年前に死亡。 |
| お く に |
与作の娘。14歳。 |
| 市 五 郎 |
くにの亭主。 |
| 川辺弥左衛門 |
上総国の代官。市五郎の親戚。 |
| 北上主水正 |
大目付。8500石の旗本。 |
| 青山稲葉守 |
寺社奉行。北上とは縁戚関係。 |
| 酒井讃岐守忠音 |
筆頭老中。 |
| 大岡 忠相 |
南町奉行。 |
| 文 吉 |
飛脚。 |
| 浪 人 |
呪術師。烏天狗に似た大男。文中には名前の表記は無し。 |
| お る い |
浪人の女房。 |
| 新 太 郎 |
浪人とるいの息子。3歳。 |
| 大久保忠興 |
小田原藩藩主。 |
| 大美五三郎 |
小田原藩士。 |
| 大川丑之助 |
小田原藩士。 |
| 蒲生 平蔵 |
小田原藩士。 |
| 村井 |
小田原藩士。 |
| 里見 |
小田原藩士。 |
| お こ よ |
五三郎の女房。 |
| お か ね |
丑之助の女房。 |
| 田中 丘隅 |
高名な農政家。54歳。 |
| 小林 |
代官所の手代。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
鎌倉幕府2代将軍を父に、木曽義仲の娘を母に持つ鞠子は、竹御所と呼ばれる屋敷にひっそりと暮らしていた。しかし、幕府内では非情な権力争いが続き、源氏の血縁者が一人また一人と亡くなっている。そして鞠子の周辺も次第にきな臭い風が吹きはじめようとしていた・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
比企ヶ谷・・・「竹御所」と呼ばれる鞠子が住む屋敷があります。
 |
比企ヶ谷は現在の妙本寺があるあたりの谷戸のことをいいます。 |
長禅寺・・・浄妙は下野国池辺郷から名越の長禅寺へ向かう途中、竹御所に助けを求めてきます。
 |
長禅寺(長善寺)は、かつて名越にありましたが、後に大町へ移り江戸時代に消失してしまいました。
現在は辻の薬師堂のみ現存しています。
また、「下野国池辺郷」は現在の栃木県小山市の南部辺りになります。 |
|
|
| 登場人物 |
| 鞠 子 |
「竹御所」と呼ばれる屋敷に住む源氏の姫。 |
| 源 頼家 |
鞠子の父。鎌倉幕府2代将軍。死亡。 |
| 刈 藻 |
鞠子の母。 |
| 木曽 義仲 |
刈藻の父。死亡。 |
| 木曽 義高 |
義仲の子。死亡。 |
| 巴 |
義仲の愛妾。 |
| 今井 兼平 |
巴の兄。死亡。 |
| 源 頼朝 |
鞠子の祖父。頼家の父。鎌倉幕府初代将軍。死亡。 |
| 北条 政子 |
鞠子の祖母。頼朝の妻。頼朝の死後、「尼御台」と呼ばれる。 |
| 大 姫 |
頼朝の長女。死亡。 |
| 一 幡 |
頼家の長男。比企氏の娘との子。死亡。 |
| 善 哉 |
頼家の二男。法名「公暁」。 |
| 千 寿 |
頼家の三男。法名「栄実」。 |
| 花 若 |
頼家の四男。法名「禅暁」。 |
| 源 実朝 |
頼家の弟。鎌倉幕府3代将軍。 |
| 坊門信清女 |
実朝の妻。 |
| 小 宰 相 |
刈藻の世話をする女房。 |
| 浄 妙 |
鞠子が助けた旅の小尼。その後「妙」と名乗る。 |
| 諏訪六郎雅兼 |
鞠子の近習。後に鞠子と夫婦になる。 |
| 江戸左衛門尉義範 |
鞠子の近習。 |
| 海野小太郎幸氏 |
大姫付きの小姓。 |
| 北条小四郎義時 |
幕府の御家人。鎌倉幕府2代執権。 |
| 伊 賀 局 |
義時の後妻。本名「伊賀光子」。 |
| 伊賀 朝光 |
伊賀局の父。 |
| 伊賀 光宗 |
伊賀局の兄。 |
| 北条修理亮泰時 |
幕府の御家人。義時の子。 |
| 北条次郎朝時 |
幕府の御家人。義時の子。 |
| 北条 時房 |
幕府の御家人。義時の弟。 |
| 北条 重時 |
幕府の御家人。 |
| 北条 政村 |
幕府の御家人。 |
| 北条大炊ノ介有時 |
幕府の御家人。 |
| 和田 義盛 |
幕府の御家人。侍所別当。 |
| 朝比奈三郎義秀 |
幕府の御家人。義盛の子。 |
| 和田四郎義直 |
幕府の御家人。義盛の子。 |
| 和田五郎義重 |
幕府の御家人。義盛の子。 |
| 和田新左衛門常盛 |
幕府の御家人。義盛の子。 |
| 和田平太胤長 |
幕府の御家人。義盛の甥。 |
| 大江 広元 |
幕府の御家人。政所別当。 |
| 三浦 義村 |
幕府の御家人。善哉の乳父。 |
| 三浦駒若丸 |
幕府の御家人。義村の子。 |
| 泉小次郎親衡 |
幕府の御家人。千寿の乳父。 |
| 千葉介成胤 |
幕府の御家人。 |
| 長沼五郎宗政 |
幕府の御家人。 |
| 千葉 胤綱 |
幕府の御家人。 |
| 堀藤次親家 |
幕府の御家人。 |
| 藤内 光澄 |
親家の郎従。 |
| 三 寅 |
後の鎌倉幕府4代将軍「九条頼経」。 |
| 阿静坊安念 |
親衡の腹心の僧。 |
| 定 暁 |
鶴岡八幡宮の別当。 |
| 忍 寂 |
鶴岡八幡宮の社僧。 |
| 畠山 重慶 |
畠山一族の末裔。日光山別当坊で修行中の身。 |
| 池ノ禅尼 |
平清盛の継母。 |
| 公 胤 |
円城寺の僧。善哉の師。 |
| 陳 和 卿 |
宋人の工匠。 |
| 後白河法皇 |
第77代天皇。院政を敷く朝廷の実力者。 |
| 後鳥羽上皇 |
第82代天皇。後白河の孫。 |
| 卿ノ二位 |
後鳥羽の乳母。本名「藤原兼子」。 |
| 伊 賀 局 |
後鳥羽の愛妾。 |
| 土御門上皇 |
第83代天皇。後鳥羽の子。 |
| 順徳 上皇 |
第84代天皇。後鳥羽の子。 |
| 西園寺公経 |
公卿。 |
| 西園寺実氏 |
公卿。公経の子。 |
| 九条 道家 |
公卿。公経の娘婿。 |
| 浄 蓮 |
伊豆の走湯権現の僧。 |
|
| . |
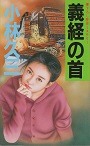 |
|
あらすじ
女子大生の速水直子は、狭心症の疑いで入院中の特捜検事・室井政行と歴史談義に花を咲かせていた。直子の恋人の及川研一は、直子の卒論のテーマが「平家物語」と聞いて歴史好きの叔父・室井を紹介したのだ。退屈な入院生活で暇を持て余していた室井としても格好の話し相手になったのだ。室井は「平家物語」と聞いて「二人の義経の謎」の話題を切り出し、さらに「義経=成吉思汗説」へと話を発展させていく・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・源義経は八幡宮若宮の上棟式に出席します。
|
|
| 登場人物 |
| 室井 正行 |
東京地検特捜部検事。狭心症で入院中。 |
| 速水 直子 |
梨花女子大学文学部国文学科4年生。22歳。 |
| 及川 研一 |
直子の恋人。室井の甥。城和大学経済学部卒業後、東洋航空広報部勤務。23歳。 |
| 小谷部金一郎 |
「義経は成吉思汗也」の著者。 |
| 中島 広幸 |
西北大学歴史学助教授。 |
| 沢 史生 |
民俗史研究家。 |
| 話題に登場する歴史上の人物(例え話などを拾えば下記の他にかなりの数の歴史上の人物がでてきます。) |
| 源九郎義経 |
幼名・牛若丸。悲劇の英雄。 |
| 武蔵坊弁慶 |
義経の腹心。 |
| 伊勢義盛 |
義経の家来。 |
| 佐藤四郎忠信 |
義経の家来。 |
| 伊豆右衛門尉有綱 |
義経の家来。 |
| 堀弥太郎景光 |
義経の家来。 |
| 鈴木三郎重家 |
義経の家来。 |
| 亀井六郎浩重 |
義経の家来。 |
| 五郎丸 |
義経の小舎小童。 |
| 静 |
義経の妻。 |
| 山本 義経 |
もうひとりの「義経」。源氏の血を引く近江国の武士。左兵衛尉。 |
| 柏木 義兼 |
山本義経の弟。 |
| 柏木 義弘 |
義兼の子。 |
| 源 義朝 |
九郎の父。 |
| 常盤御前 |
九郎の母。 |
| 源 頼朝 |
九郎の長兄。 |
| 源 範頼 |
九郎の次兄。 |
| 大江 広元 |
幕府の御家人。 |
| 梶原 景時 |
幕府の御家人。 |
| 和田 義盛 |
幕府の御家人。 |
| 土肥 実平 |
幕府の御家人。 |
| 土佐坊昌俊 |
幕府の御家人。 |
| 千葉介常胤 |
幕府の御家人。 |
| 八田 知家 |
幕府の御家人。 |
| 一条大蔵卿 |
九郎の育ての親。 |
| 吉次 伝高 |
金商人。 |
| 聖弘 得業 |
興福寺の僧。 |
| 藤原 範季 |
朝廷の木工頭。 |
|
・・・・などなど。 |
|
| . |
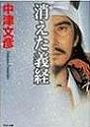 |
|
あらすじ
平泉の戦乱を逃れた源義経が、靺鞨の国から騎馬軍団をつれて陸奥に戻ってくるという。そこで幕府は、その真偽を確かめるべく佐貫坊と善知坊を陸奥へ送った。そして陸奥に着いた二人は、海の向こうから船がやってくるのを目撃する・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・源頼朝が妻の政子、子の頼家とともに初詣に向かいます。
|
|
| 登場人物 |
| 讃岐坊天恢 |
本名・佐貫ノ藤太。安房国佐貫郷の武士。 |
| 善知坊尭俊 |
本名・長田五兵衛。伊勢国の武士。 |
| 摂津坊雄允 |
羽黒山の修験者。 |
| 西塔坊弁生 |
羽黒山の修験者。 |
| 日向坊良全 |
羽黒山の修験者。 |
| 大東坊 |
羽黒山の修験者。大男。 |
| 八坂坊 |
羽黒山の修験者の長老格。 |
| 相模坊 |
元・羽黒山の修験者。本名・鎌田盛政。一ノ谷の合戦で戦死。 |
| 鎌田 光政 |
盛政の弟。屋島の合戦で戦死。 |
| 信濃坊 |
熊野の修験者の長老格。 |
| 早苗 |
熊谷直実の遠縁の娘。幕府の雑色。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。 |
| 北条 政子 |
頼朝の妻。「尼将軍」。 |
| 源 頼家 |
頼朝の長男。後の2代将軍。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。政子の父。 |
| 大江 広元 |
幕府の有力御家人。頼朝の腹心。 |
| 上総介広常 |
幕府の有力御家人。 |
| 千葉介常胤 |
幕府の有力御家人。 |
| 一条 能保 |
幕府の有力御家人。 |
| 和田 義盛 |
幕府の有力御家人。侍所別当。 |
| 梶原 景季 |
幕府の御家人。 |
| 土佐坊昌俊 |
幕府の御家人。 |
| 小浜作左衛門 |
和田家の家人。 |
| 三島権之助 |
三浦家の家人。 |
| 源九郎義経 |
頼朝の弟。 |
| 武蔵坊弁慶 |
義経の腹心。 |
| 常陸坊海尊 |
義経の家来。 |
| 伊勢三郎能盛 |
義経の家来。 |
| 鷲尾三郎経春 |
義経の家来。 |
| 堀弥太郎景光 |
義経の家来。 |
| 佐藤 忠信 |
義経の家来。 |
| 佐藤 継信 |
義経の家来。 |
| 鈴木三郎重家 |
義経の家来。 |
| 亀井六郎重清 |
義経の家来。 |
| 静 |
義経の愛妾。 |
| 藤原 秀衡 |
奥州藤原氏の当主。 |
| 藤原 国衡 |
秀衡の長男。 |
| 藤原 泰衡 |
秀衡の次男。 |
| 藤原 忠衡 |
秀衡の三男。 |
| 藤原 基成 |
秀衡の舅。 |
| 佐藤 元治 |
藤原家の腹心。 |
| 板橋 長治 |
藤原家の腹心。 |
| 河田 次郎 |
藤原家の腹心。 |
| 安東 秀元 |
藤原家の腹心。 |
| 杉ノ目太郎行信 |
藤原家の家人。 |
| 茜 |
忠衡の館の下女。 |
| 西行 |
漂泊の人生を歩む歌詠みの法師。 |
| 後白河法皇 |
朝廷の権力者。 |
| 丹後局 |
法皇の寵妃。 |
| 高階 泰経 |
公家。大蔵卿。 |
| 高階 頼経 |
公家。刑部卿。泰経の息子。 |
| 九条 兼実 |
公家。右大臣。 |
| 藤原 基道 |
公家。摂政。 |
| 国光 |
朝廷の使者役。史生。 |
| 守康 |
朝廷の使者役。史生。 |
| 景弘 |
朝廷の使者役。院司。 |
| 聖弘 |
奈良興福寺の僧。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
食い道楽の作家・村井弦斎は小説の執筆のために、同郷の後輩・山田文彦が働く大磯の旅館「祷龍館」を訪ねた。しかし、その祷龍館には異人の女幽霊が出るという噂がたっていた。好奇心旺盛な弦斎は、早速その謎に挑むのだが・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・弦斎、文彦、ベーカー博士夫妻は、馬車で鎌倉見物をする際に鶴岡八幡宮に立ち寄ります。
高徳院・・・八幡宮参拝後、4人は長谷の大仏を見に高徳院にも寄ります。 |
|
| 登場人物 |
| 村井 弦斎 |
グルメ小説家。元報知新聞編集長。35歳。 |
| 山田 文彦 |
大磯の旅館「祷龍館」の医学助手。25歳。 |
| 尾崎多嘉子 |
後藤象二郎伯爵の姪。 |
| 尾崎 卯作 |
多嘉子の父。肥前佐賀藩士。 |
| 伊良山 |
男爵。 |
| 伊良山 修 |
男爵の息子。 |
| 松本 順 |
大磯に住む陸軍軍医総監。文彦の恩師。 |
| 唐沢嘉右衛門 |
横浜の「薄荷屋敷」と呼ばれる館に住む貿易商。50歳。 |
| 唐沢 涼子 |
嘉右衛門夫人。30歳。 |
| ロジャー・ヴァリー |
慶応義塾の英語教師。 |
| アイリーン・ヴァリー |
ロジャーの娘。多嘉子の英語の家庭教師。 |
| ジェームス・A・ベーカー |
弦斎がアメリカ遊学時代に世話になった医学博士。 |
| 尾上菊五郎 |
歌舞伎役者。 |
| 森 三之助 |
歌舞伎役者。横浜賑座の看板役者。 |
| 玉梓 吉弥 |
歌舞伎役者。横浜賑座の売り出し中の女形。 |
| 高木 |
「祷龍館」の料理長。 |
| 梅 |
「祷龍館」の部屋係。 |
| 伊藤 博文 |
別荘「滄浪閣」に住む明治の元勲。 |
| 大隈 重信 |
憲政党党首。伯爵。 |
| 大隈 綾子 |
重信夫人。 |
| 円城寺 清 |
重信の広報担当官。元報知新聞記者。弦斎の後輩。 |
| 北島正之助 |
神戸の資産家。 |
| 北島小夜子 |
正之助の娘。 |
| 永倉 留吉 |
北島家のコック。元銀座の「煉瓦亭」コック。永倉新八の甥。 |
| 吉田松五郎 |
大磯で牛乳搾取販売業「吉田牧牛舎」経営。 |
| 吉田 松吉 |
松五郎の息子。 |
| 間宮 宇山 |
「鴫立庵」庵主。 |
| 富貴楼お倉 |
芸者。元・幕府鉄砲師の妻。 |
| 小りん |
お倉お抱えの芸妓。 |
| 日高 権造 |
警視庁警部。 |
| 南郷 |
大磯署巡査。 |
|
| . |
 |
| 逆襲 蒙古襲来 鎌倉陥落 |
柘植久慶 |
C★NOVELS |
|
あらすじ
モンゴル皇帝・クビライは再度日本へ遠征軍を派遣することを決定した。そして兵を二手にわけ、忻都ら率いる高麗軍は博多を、御厨ら率いる江南軍は鎌倉を攻略しようとしていた。果たして鎌倉幕府軍は、モンゴルの来襲を防ぐことはできるのか・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
七里ガ浜・・・鎌倉を攻めようとしている江南軍の唐操嵐は、七里ガ浜から上陸する作戦をとります。
大慈寺・・・頼綱は、大慈寺付近で苦戦を強いられます。
|
大慈寺は、源実朝が建てた寺で「大倉新御堂」とも呼ばれていました。
現在の明王院の東あたりにありましたが、廃寺となっています。 |
|
|
| 登場人物 |
| 唐 操 嵐 |
江南軍の将。正体は「御厨太郎」。 |
| 御厨 太郎 |
歴史ノンフィクション作家。正体は三浦一党の生き残り「三浦景継」。
タイムスリップをして史実を変えたいと狙っている。 |
| 汪 忍 |
江南軍の将。正体は「扇谷早苗」。 |
| 扇谷 早苗 |
御厨の許嫁。名前は「忍」。 |
| 扇谷 継信 |
早苗の父。 |
| 怱 必 烈 |
大元帝国の皇帝。「クビライ」。 |
| 忻 都 |
高麗軍の元帥。 |
| 洪 茶 丘 |
高麗軍の元帥。 |
| 金 方 慶 |
高麗軍の元帥。 |
| 波 央 |
高麗軍の将。幕僚。 |
| 盧 仁 哲 |
高麗軍の将。幕僚。 |
| 呉 英 傑 |
高麗軍の将。幕僚。 |
| 金 白 虎 |
高麗軍の部隊長。 |
| 白 聖 虎 |
高麗軍の航海士。 |
| 阿 塔 海 |
江南軍の元帥。 |
| 康 操 雲 |
江南軍の元帥。 |
| 劉 復 亨 |
江南軍の副元帥。 |
| 藩 科 連 |
江南軍の将。幕僚。 |
| 范 文 虎 |
江南軍の将。 |
| 李 強 |
江南軍の連隊長。 |
| 張 永 清 |
江南軍の部隊長。 |
| 李 賢 了 |
江南軍の航海士。 |
| 林 大 年 |
江南軍の航海士。 |
| 周 少 偉 |
江南軍の航海士。 |
| 北条 時宗 |
鎌倉幕府8代執権。 |
| 北条 兼時 |
時宗の甥。長門探題。 |
| 北条 宗政 |
時宗の弟。 |
| 安達 泰盛 |
幕府の重臣。 |
| 平 頼綱 |
鎌倉幕府の御家人。 |
| 長谷 正継 |
鎌倉幕府の御家人。 |
| 笠懸 義正 |
鎌倉幕府の御家人。 |
| 竹崎 季長 |
肥後の地頭。 |
| 御厨 是常 |
松浦一党の将。 |
| 武藤 経資 |
太宰少弐。 |
| 武藤 資時 |
経資の息子。 |
| 河野 通有 |
瀬戸内海の水軍の長。 |
| 十郎次 |
通有の手下。 |
| 間庭清十郎 |
下田の地頭。 |
| 青野 勘助 |
間庭の使者。 |
| 荘助 |
下田の漁師。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
お上からの弾圧をうけ鎌倉に謹慎していた風刺画家の高橋健吾のもとに、新聞社に勤める親友の手塚満男が訪ねてきた。貧民窟でおこった殺人事件に、どうやら右翼結社「野太党」の党首・野々山太一郎が関わっているというのだ。手塚はその事件を調べて記事にし、野々山の鼻をあかしてやろうとするのだが、逆に野々山一派に拘束されてしまう・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
若宮大路・・・「天富一座」の見世物小屋は、若宮大路に近い神社に建ちました。
鶴岡八幡宮・・・健吾が謹慎していた小料理屋「静久」は、八幡宮前にあります。 |
|
| 登場人物 |
| 高橋 健吾 |
風刺画家。弾圧され鎌倉で謹慎中の身。 |
| 手塚 満男 |
「萬珍新聞」主幹。健吾の親友。 |
| 野々山太一郎 |
右翼結社「野太党」党首。 |
| 磯田 晋 |
右翼結社「野太党」党員。 |
| お富 |
旅芸人一座「天富一座」の座長。 |
| 捨吉 |
「天富一座」の老人。 |
| 真由 |
「天富一座」の少女。不思議な力が宿る。 |
| 権じいさん |
鶴岡八幡宮前小料理屋「静久」の主人。 |
| お清ばあさん |
権じいさんの妻。健吾の世話をする。 |
| お宮 |
健吾の許嫁。 |
| 大野 苗吉 |
秩父の農民。「風布組」をつくり、「国民党」へ加担する。 |
| 野間土佐衛門 |
東京の貧民窟に住む総代。 |
| 岡部 賢三 |
呆坊の仲間。 |
| 松・竹・梅 |
秩父に住む三つ子の老婆。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
六条大橋で、弁慶が出会った小童は迦楼羅の面をつけていた。そして鮮やかな身のこなしで弁慶をかわすその小童は、「遮那王」と名乗った。その後、「源義経」と名を改めた遮那王だが、弁慶は迦楼羅の面をつける義経に疑念を抱く・・・。
|
|
| 作品の舞台 |
若宮大路・・・喜三太たちは、若宮大路で静と再会します。
腰越・・・壇ノ浦の合戦で勝利した義経は、腰越で兄・源頼朝の知らせを待ちます。 |
|
| 登場人物 |
| 源 義経 |
幼名「遮那王」。身のこなしが軽く迦楼羅の面をつけて行動する。 |
| 武蔵坊弁慶 |
義経の家来。怪力。 |
| 常陸坊海尊 |
義経の家来。杖術の達人。 |
| 熊野喜三太 |
義経の家来。馬の使い手。 |
| 伊勢三郎義盛 |
義経の家来。元・山賊。 |
| 佐藤 継信 |
義経の家来。元・藤原氏の家臣。 |
| 佐藤 忠信 |
義経の家来。元・藤原氏の家臣。継信の弟。剣の達人。 |
| 鎌田 正近 |
義経の家来。 |
| 鷲尾 三郎 |
義経の家来。 |
| 片岡太郎経春 |
義経の家来。源氏ゆかりの武士。 |
| 片岡八郎為春 |
義経の家来。源氏ゆかりの武士。 |
| 鈴木三郎重家 |
義経の家来。源氏ゆかりの武士。 |
| 亀井六郎重清 |
義経の家来。源氏ゆかりの武士。 |
| 備前平四郎 |
義経の家来。 |
| 玄倶院寂円 |
義経の家来。海尊の弟子。火傷を負い黒僧頭巾をしている。 |
| 静 |
義経の愛妾。都随一の白拍子。 |
| 源 義朝 |
義経の父。平治の乱で戦死。 |
| 由良 |
義朝の正室。頼朝の母。 |
| 常盤 |
義朝の愛妾。義経の母。 |
| 源 頼朝 |
鎌倉幕府初代将軍。源氏の棟梁。義経の兄。 |
| 源 範頼 |
頼朝の弟。蒲冠者。 |
| 源 義仲 |
頼朝・義経の従兄弟。朝日将軍。 |
| 源 義高 |
義仲の子。 |
| 源 行家 |
頼朝の叔父。義朝の弟。 |
| 源 頼政 |
源氏の長老。 |
| 源 博綱 |
頼政の子。 |
| 北条 時政 |
鎌倉幕府初代執権。 |
| 北条 政子 |
時政の娘。頼朝の妻。後の「尼将軍」。 |
| 梶原 景時 |
鎌倉幕府の有力御家人。戦目付。 |
| 和田 義盛 |
鎌倉幕府の有力御家人。侍所別当。 |
| 畠山 重忠 |
鎌倉幕府の有力御家人。 |
| 上総介広常 |
鎌倉幕府の有力御家人。 |
| 熊谷 直実 |
鎌倉幕府の有力御家人。 |
| 熊谷 直家 |
鎌倉幕府の御家人。直実の息子。 |
| 河越太郎重頼 |
鎌倉幕府の御家人。 |
| 若 |
重頼の娘。義経の正室。 |
| 土佐坊昌俊 |
鎌倉幕府の御家人。 |
| 佐々木高綱 |
源氏方の部将。 |
| 土岐 実平 |
源氏方の部将。 |
| 平山 季重 |
源氏方の部将。 |
| 成田 五郎 |
源氏方の部将。 |
| 長崎 太郎 |
源氏方の部将。 |
| 河田 次郎 |
源氏方の部将。 |
| 武田 信義 |
源氏方の部将。 |
| 那須 与一 |
源氏方の武士。 |
| 岡部六弥太 |
源氏方の武士。 |
| 後白河法皇 |
第77代天皇。退位後、院政を行う。 |
| 高倉 天皇 |
第80代天皇。後白河の第7皇子。 |
| 安徳 天皇 |
第81代天皇。高倉の |
| 平 清盛 |
平家の棟梁。太政大臣。 |
| 平 時子 |
清盛の正室。後の「二位の尼」。 |
| 平 徳子 |
清盛の次女。高倉天皇に嫁ぐ。安徳の母。後の「建礼門院」。 |
| 平 宗盛 |
清盛の三男。 |
| 平 知盛 |
清盛の四男。中納言。 |
| 平 経盛 |
清盛の弟。 |
| 平 敦盛 |
経盛の子。 |
| 平 忠度 |
清盛の弟。薩摩守。 |
| 平 教経 |
清盛の甥。 |
| 平 通盛 |
清盛の甥。 |
| 平 継盛 |
清盛の孫。 |
| 城 助職 |
平家方の部将。 |
| 平 盛俊 |
平家方の部将。 |
| 今井 兼平 |
平家方の部将。 |
| 大庭 景親 |
平家方の部将。 |
| 藤原 季範 |
公家。由良の父。 |
| 藤原 長成 |
公家。「一条大蔵卿」と呼ばれる。常盤の再婚相手。 |
| 富樫左衛門泰家 |
安宅関の関守。 |
| 藤原 秀衡 |
奥州藤原氏の棟梁。奥州鎮守府将軍。 |
| 藤原 倫子 |
秀衡の正室。 |
| 栂の前 |
秀衡の側室。 |
| 藤原 国衡 |
秀衡の長男。 |
| 藤原 泰衡 |
秀衡の次男。 |
| 藤原 薫子 |
国衡・泰衡の妹。 |
| 藤原 忠衡 |
国衡・泰衡の異母弟。 |
| 吉次 信高 |
陸奥国の金掘の頭領。黄金商人。 |
| 蓮忍 |
東光坊の阿闍梨。 |
|
| . |
 |
|
あらすじ
隈本藩士・貴月主馬の妻・うねは祖国・朝鮮との縁を切るために鎌倉の東慶寺に駆け込んだ。朝鮮から日本で永住する朝鮮人を強制帰国させようと朝鮮使節団が来日したからだ。この件に関しては幕府内でも意見が二分し、朝鮮びいきの大御所・徳川秀忠は年寄の土井利勝を使い東慶寺に圧力をかけようとしていた。一方、三代将軍の徳川家光は幼い頃の初恋相手だった涼姫が「天秀尼」として住持をつとめている東慶寺を守るべく、兵法師範役の柳生但馬守宗矩に事を解決するよう命じた。そこで女人禁制の寺を守るため、宗矩は大和柳生庄で暮らす宗矩の娘・矩香を東慶寺に入山させた…。
|
|
| 作品の舞台 |
鶴岡八幡宮・・・十兵衛と喜左衛門が詣でます。
円覚寺・・・十兵衛と喜左衛門が詣でます。
東慶寺・・・矩香はうねを守るために入山し、数々の敵と戦います。
|
|
| 登場人物 |
| 柳生但馬守宗矩 |
江戸将軍家兵法指南役。三千石の旗本。 |
| 柳生 矩香 |
宗矩の長女。大和柳生庄の姫。 |
| 柳生十兵衛三厳 |
宗矩の長男。18歳。矩香の弟。 |
| 柳生 友矩 |
宗矩の次男。十兵衛の異母弟。13歳。 |
| 柳生 友景 |
宗矩の従兄弟。 |
| 徳川 家光 |
江戸幕府3代将軍。 |
| 徳川 秀忠 |
大御所。家光の父。2代将軍。 |
| 松平長四郎信綱 |
家光の懐刀。小姓頭六人衆の一人。知恵伊豆。 |
| 土井大炊頭利勝 |
家光の重臣。西の丸の年寄。 |
| 千姫 |
家光の姉。 |
| 天秀尼 |
東慶寺20世住持。千姫の養女。家光の初恋相手。幼名は「涼姫」。 |
| 桂香尼 |
東慶寺の尼。 |
| 賀蘭尼 |
東慶寺の尼。 |
| 加藤肥後守忠広 |
隈本藩五十四万石の二代藩主。父は加藤清正。 |
| 加藤右馬允 |
隈本藩筆頭家老。 |
| 鷹ノ巣康祐 |
隈本藩士。 |
| 津田慎兵衛 |
隈本藩士。 |
| 保宮与五郎 |
隈本藩士。 |
| 野々村進吾 |
隈本藩士。 |
| 貴月 主馬 |
隈本藩物頭。 |
| 貴月 うね |
主馬の妻。朝鮮人。 |
| 貴月啓之進 |
主馬の長男。 |
| 貴月誠二郎 |
主馬の次男。 |
| 貴月宗三郎 |
主馬の三男。 |
| 庄田喜左衛門 |
宗矩の高弟。 |
| 出淵平兵衛 |
宗矩の父・石舟斎の高弟。 |
| 笹森 甚内 |
柳生家用人。 |
| 篠田菊四郎 |
宗矩配下の若侍。 |
| 堀田新兵衛 |
宗矩配下の若侍。 |
| 徳川 忠長 |
駿河藩主。家光の弟。駿河大納言。漢名呼称は「駿河黄門」。 |
| 鳥居 成次 |
駿河藩附家老。土佐守。 |
| 加納軍大夫 |
駿河藩士。 |
| 汐風城之介 |
矩香の婚約者。小野派一刀流門下。大怪我をする。 |
| 汐風勘兵衛幸親 |
城之介の父。旗本。 |
| 壮 帆之介 |
利勝の懐刀。大盗・向坂甚内の遺児。 |
| 九十九半四郎 |
帆之介の配下。元・広島藩士。 |
| 小野 忠明 |
利勝の目付。65歳。兵法指南役。旧名は「御子神典膳」。 |
| 箙 幻薫斎 |
幕府三忍軍(伊賀・甲賀・根来)忍び組の頭領。 |
| 百舌 |
伊賀の忍者。 |
| 幕屋 大休 |
矩香の幼馴染みで剣の好敵手。松永家家臣・戒重肥後守の遺児。幼名は「織部之介」。 |
| 呉 惟忠 |
明国の副総監。 |
| 鄭 岦 |
朝鮮使節団正使。 |
| 姜 広重 |
朝鮮使節団副使。 |
| 辛 啓栄 |
朝鮮使節団従事官。 |
| 南 師今 |
朝鮮使節団正使。 |
| 小笠原源信斎長治 |
朝鮮使節団第二代理人。真新蔭流の遣い手。 |
|
| . |
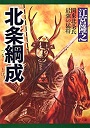 |
北条綱成
関東北条氏最強の猛将 |
江宮隆之 |
PHP文庫 |
|
あらすじ
今川家の重臣にして剛将・福島上総介正成は繰り返された甲斐武田氏との戦いの中戦死した。正成の嫡子・勝千代は福島一門の数名と共に落ちたが、やがて関東の雄・北条氏綱の目にとまり嫡男・氏康を支える「北条綱成」として戦国の世を駆けて行った…。
|
|
| 作品の舞台 |
鎌倉・・・足利義明の進軍に備え、北条氏綱は鎌倉を占拠します。
鶴岡八幡宮・・・焼失した八幡宮を北条氏が造営します。
玉縄・・・北条綱成は居を河越城から、玉縄城に移します。
|
|
| 登場人物 |
| 北条孫九郎綱成 |
第3代玉縄城主。河越城代。正成の嫡男。幼名・勝千代。地黄八幡の旗を掲げ戦場をかける。 |
| 福島上総介正成 |
綱成の父。今川家の将。遠州土方城主。武田氏との戦いで戦死する。 |
| 福島 基正 |
正成の父。綱成の祖父。今川家の家老格。 |
| 朝日姫 |
綱成の正室。氏綱の次女。氏康の長妹。 |
| 北条善九郎氏繁 |
綱成の嫡男。4代目玉縄城主。 |
| 北条弥二郎氏秀 |
綱成の次男。 |
| 梅 |
氏繁の正室。氏康の次女。 |
| 北条 氏舜 |
氏繁の嫡男。 |
| 北条 氏勝 |
氏繁の次男。 |
| 堀内 忠春 |
正成の従弟。 |
| 福島孫四郎綱房 |
正成の次男。綱成の弟。 |
| 福島十郎助昌 |
正成の遠縁。今川家の将。遠州宇津山城主。 |
| 福島彦十郎 |
助昌の嫡男。 |
| 福島孫四郎 |
助昌の次男。 |
| 斎藤左近将監 |
正成の遠縁。駿州久能山城主。 |
| 福島安房守 |
十郎の従兄。遠州丸子城主。 |
| 山県淡路守 |
福島家家臣。副将格。 |
| 篠原刑部少輔 |
福島家家臣。 |
| 北条 早雲 |
今川家の軍師兼伊豆守護。北条氏初代当主。伊勢新九郎。 |
| 北条新九郎氏綱 |
早雲の嫡男。北条氏2代目当主。 |
| 北条新六郎氏時 |
早雲の次男。初代玉縄城主。 |
| 北条 長綱 |
早雲の三男。武州小机城主。後の「北条幻庵宗哲」。 |
| 北条新九郎氏康 |
氏綱の嫡男。北条氏3代目当主。綱成と同じ年齢。 |
| 北条彦九郎為昌 |
氏綱の三男。2代目玉縄城主。河越城主。綱成・綱房の養父。 |
| 北条助九郎氏尭 |
氏綱の四男。 |
| 北条新九郎氏政 |
氏康の次男で嫡男。北条氏4代目当主。長男は早逝。 |
| 北条 氏照 |
氏康の三男。 |
| 北条 氏邦 |
氏康の四男。 |
| 北条 氏規 |
氏康の五男。豆州韮山城主。 |
| 妻 |
氏規の正室。綱成の長女。 |
| 北条 氏直 |
氏政の嫡男。北条氏5代目当主。 |
| 松田七郎兵衛憲秀 |
北条家家臣。家老格。 |
| 笠原新六郎 |
北条家家臣。憲秀の長男。伊豆の郡代。 |
| 松田三郎兵衛 |
北条家家臣。憲秀の三男。 |
| 大道寺盛昌 |
北条家家臣。氏綱の従弟。鶴岡八幡宮造営奉行。河越城主。 |
| 太田 資高 |
北条家家臣。江戸城主。 |
| 太田 資貞 |
北条家家臣。資高の弟。 |
| 重田木工之助 |
北条家家臣。 |
| 大藤與次郎 |
北条家家臣。 |
| 太田弾正忠 |
北条家家臣。 |
| 竹本 源三 |
北条家家臣。 |
| 遠山 綱景 |
北条家家臣。 |
| 富永 直勝 |
北条家家臣。 |
| 内藤大和守綱秀 |
北条家家臣。 |
| 山中 主膳 |
北条家家臣。 |
| 太田 氏資 |
北条家家臣。武州岩付城主。 |
| 酒井 胤治 |
北条家家臣。上総土気城主。 |
| 風魔小太郎 |
北条氏の忍び。初代風魔党首領。 |
| 風魔小太郎 |
北条氏の忍び。2代目風魔党首領。通称・鬼太郎。 |
| 風魔 幻舟 |
鬼太郎の叔父。忍びの首領。 |
| 今川 氏親 |
駿河守護。今川家当主。今川氏9代目当主。幼名・龍王丸。 |
| 北川殿 |
氏親の母。早雲の妹。 |
| 中御門氏 |
氏親の正室。後の「寿桂尼」。 |
| 側室 |
氏親の側室。正成の妹。 |
| 今川 氏輝 |
氏親の嫡男。今川氏10代目当主。 |
| 今川彦五郎 |
氏親の次男。 |
| 玄広恵探 |
氏親の三男。後に花倉の遍照光寺の住持。 |
| 梅岳承芳 |
氏親の五男。幼名・方菊丸。後の「今川義元」。 |
| 九英承菊 |
今川家の軍師。黒衣の臨済僧。後の「大原崇孚雪斎」。 |
| 庵原 忠房 |
今川家家臣。 |
| 瀬名 氏俊 |
今川家家臣。 |
| 朝比奈泰能 |
今川家家臣。 |
| 朝比奈泰朝 |
今川家家臣。泰能の嫡男。 |
| 岡部 親綱 |
今川家家臣。 |
| 由比助四郎 |
今川家家臣。遠州由比城主。 |
| 小鹿 範満 |
今川家家臣。 |
| 武田 信虎 |
甲斐守護。武田氏15代当主。 |
| 大井夫人 |
信虎の正室。 |
| 武田 晴信 |
信虎の嫡男。武田氏16代当主。後の「武田信玄」。 |
| 荻原常陸介昌勝 |
武田家の軍師。信虎の傅役。 |
| 多田 満頼 |
武田家家臣。 |
| 横田 高松 |
武田家家臣。 |
| 穴山 信綱 |
武田家家臣。 |
| 小幡 日浄 |
武田家家臣。 |
| 原 虎胤 |
武田家家臣。綱成にとって父の仇。 |
| 小山田信有 |
武田家家臣。郡内領主。 |
| 高坂 昌信 |
武田家家臣。 |
| 飯富 虎昌 |
武田家家臣。 |
| 飯富源四郎 |
武田家家臣。後の「山県昌景」。 |
| 教来石景政 |
武田家家臣。後の「馬場信春」。 |
| 小山田弾正 |
武田家家臣。郡内一の槍武者。 |
| 大井 信達 |
西郡の甲斐国人衆。 |
| 足利 政氏 |
2代古河公方。 |
| 足利 高基 |
政氏の嫡男。3代古河公方。 |
| 足利 義明 |
政氏の次男。小弓公方。僧名・空然。 |
| 足利 基頼 |
政氏の四男。 |
| 足利 義純 |
基頼の嫡男。 |
| 足利 晴氏 |
高基の嫡男。4代古河公方。 |
| 足利 義氏 |
晴氏の嫡男。5代古河公方。 |
| 上杉 定正 |
扇谷上杉家11代当主。 |
| 上杉 朝興 |
扇谷上杉家13代当主。 |
| 上杉 朝定 |
扇谷上杉家14代当主。朝興の嫡男。 |
| 上杉 顕定 |
山内上杉家11代当主。 |
| 上杉 憲房 |
山内上杉家13代当主。 |
| 上田 政広 |
上杉家家臣。武州松山城主。 |
| 難波田弾正憲重 |
上杉家家臣。武州松山城代。 |
| 太田 資正 |
上杉家家臣。武州岩付城主。 |
| 武田 信応 |
上杉家家臣。上総真利谷城主。 |
| 武田 信隆 |
信応の異母兄。 |
| 上杉 憲政 |
28代関東管領。 |
| 里見 実尭 |
安房の国人。里見家庶流。 |
| 里見 義尭 |
里見氏5代当主。実尭の嫡男。 |
| 里見 義弘 |
里見氏6代当主。義尭の嫡男。 |
| 安西 実元 |
里見家家臣。重臣。 |
| 万喜 頼定 |
里見家家臣。重臣。 |
| 正木 時茂 |
里見家家臣。重臣。 |
| 長尾 景虎 |
越後守護。後の「上杉謙信」。 |
| 長野 業正 |
上州箕輪城主。 |
|
|
  |